
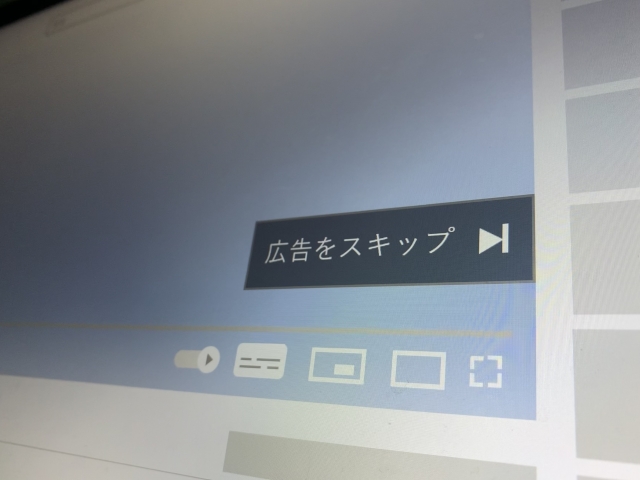
こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「広告」についてのお話です。
「自社の商品・サービスをアピールするために広告を出したいけど、どんな内容の広告にすればいいのだろうか?間違ったことを書いてはならないというのはわかるけど、他にも書いたらまずいことがあったりしないだろうか?」
このようなお悩みを抱えている事業者の方も多いのではないでしょうか。
広告は、自社の商品・サービスをアピールする上で非常に効果的であり、特にインターネットでの広告は、全国を対象としてビジネスをする上では必須といっても過言ではありません。
しかし、その内容に気を付けなければ、取締りの対象になってしまう可能性がありますし、特に、人の身体にもかかわるものについては、慎重に検討しなければなりません。
この記事では、広告規制のポイントについて解説していきます。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
SNSでインフルエンサーを起用する広告を検討しているのですが、何か注意点はありますか?
また、健康に良いことをアピールする言葉を広告に盛り込みたいのですが、問題はありますか?
目次
広告規制の主要な法律は?
広告規制で主要な法律は、いわゆる景品表示法です(正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。)。
景品表示法では、不当な表示の禁止として、主に①優良誤認表示(5条1号)、②有利誤認表示(5条2号)が定められており、これらに加えて、③告示による指定表示(5条3号)が定められています。
また、例えば医薬品、医薬部外品、化粧品については、いわゆる薬機法で特別の規制がなされています(薬機法は、正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。)。加えて、薬機法は、食品の広告でも時折問題となります。
以下では、これらの法律の規制内容やポイントについてみていきます。
景品表示法について
規制対象
まず、規制の対象となる表示(広告)には、商品、容器又は包装による広告、見本、チラシ、パンフレット、説明書面による広告、ポスター、看板などによる広告の他に、口頭や実演、インターネットによる広告等も含まれます。
そのため、商品・サービスについて対外的にアピールしようとする場合、ほとんどの場合で表示(広告)規制を受けると考えるべきです。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品・サービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、①実際のものよりも著しく優良であると示し、又は②事実に相違して競合事業者のものよりも著しく優良であると示す表示をいいます。
著しく優良であるかは、表示の受け手である一般消費者が「著しく優良」と認識するか否かがポイントになります。そして、「著しく」とは、誇張の程度が社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合をいうとされています。そのため、広告宣伝に通常含まれる程度の誇張は一般消費者の適切な選択を妨げないとして許容されると考えられています。
実際の事例では、「アセロラC」という食品に含まれるビタミンCがすべてアセロラ果実から得られた天然ビタミンであるかのように表示していたところ、実際にはアセロラ果実から得られたものではなかったため、優良誤認表示とされたものがあります(アサヒフードアンドヘルスケア株式会社に対する排除措置命令平成16年(排)第14号)。この例では、一般消費者は天然由来であることに優位性を感じると考えられたのだと理解できます。
また、効果・性能に関する表示(例えば「使えば使うほど切れ味は鋭利になる包丁」等)については、表示が実際の効果・性能と合致していることを証明するために、表示の裏付けとなる合理的な根拠として試験・調査の結果などを提出する必要があり、これを適時に提出できなければ優良誤認表示とみなされてしまうことになりますので、このような表示を検討する場合には、十分な裏付けをもって対応することが必要になります。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のもの又は競合事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を言います。
誤った表示により顧客を誘引しようとしてはならないのは当然ですが、例えば、一定の期限で限定割引があると表示していたが、実際にはいつ申し込んでも同じ割引を受けることができたような場合にも有利誤認表示に該当します。
また、二重価格表示については、実際には通常販売価格として表示する価格では販売していなかった商品について、「通常販売価格●●円から●●%オフ!」というような表示を行うことは、有利誤認表示に該当します。二重価格表示については、比較対照価格について一定期間の販売実績があるかという点がポイントになります。
告示による指定表示
景品表示法による表示規制としては、優良誤認表示や有利誤認表示の他に、告示による指定表示があります。本記事執筆現在、以下の7つが告示により指定されています。
①商品の原産国に関する不当な表示
②無果汁の清涼飲料水等についての表示
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
④おとり広告に関する表示
⑤不動産のおとり広告に関する表示
⑥有料老人ホームに関する不当な表示
⑦一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
このうち、⑦は、令和5年10月1日から新たに施行されたものであり、いわゆるステマ(ステルスマーケティング)規制です。ステマ規制とは、例えばSNSでインフルエンサーを通じて広告をしてもらうという場合に、会社から依頼されていることを明示せずにインフルエンサーが第三者的な立場から商品について発言しているように見えると、広告であるのに広告と理解されない可能性があり、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるという問題に対処するものです。
インフルエンサーを通じた広告は一般的になってきていますので、企業として適切な対応を行うのはもちろんですが、インフルエンサー側としてもステマに加担しないように注意をする必要があります。
冒頭の事例では、SNSでインフルエンサーを起用するとのことですので、ステマ規制に該当することのないよう、注意を払う必要があるといえます。
薬機法について
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器といった医薬品等をその規制対象にしており、①誇大広告等の禁止(66条)、②特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(67条)、③未承認の医薬品、医療機器および再生医療等製品の広告の禁止(68条)が定められています。
このうち、しばしば問題となるのが、①誇大広告等の禁止と③未承認の医薬品、医療機器および再生医療等製品の広告の禁止です。
特に①誇大広告等の禁止との関係では、医薬品等適正広告基準において一般化粧品について標ぼうできる効果効能が限定されており、その範囲を超えないように注意する必要があります。
また、③未承認の医薬品、医療機器および再生医療等製品の広告の禁止との関係では、医薬品的な効能・効果を標ぼうした健康食品は、薬機法の医薬品の定義との関係で薬機法上「医薬品」とされてしまう結果、その健康食品は未承認医薬品に当たり、販売に許可や届出が必要になり、また、その健康食品の広告に対しては未承認医薬品の広告規制がかかることになります。
このように、単なる広告だと軽く見ることなく、内容を精査することが非常に大切です。
冒頭の事例では、健康食品の広告を行うということなので、医薬品的な効能・効果を標ぼうしていると判断されないような文言にする必要があります。
健康食品の広告規制の詳細については、こちらの記事をご参照ください。
広告対応をおろそかにするリスク
広告対応をおろそかにし景品表示法に違反した広告を行った場合、行政指導にとどまらず措置命令(行為の差止め、再発防止措置、周知措置などが命じられる)を受ける可能性がありますし、これに従わなければ懲役や罰金の刑事罰を受ける可能性もあります。また、景品表示法では課徴金制度もあります。
さらに、薬機法の広告規制に違反すると懲役や罰金の刑事罰がありますし、未承認の医薬品を販売したことになれば医薬品の無許可販売の罪が成立し、これも懲役や罰金の刑事罰があります。
仮にこれらの対象にはならなかった場合であっても、問題のある広告を行った場合には会社としてのレピュテーションの低下は避けられませんので、広告対応をおろそかにしてはならないといえます。
広告対応を弁護士に依頼するメリット
広告は、自社の商品・サービスを訴求する上で非常に有効な手段です。
しかし、上記のように、規制に注意しながら適切な広告を行わなければ、罰則の対象となるリスクも潜んでいます。
また、最近は、法的に見れば厳密には問題ないようなケースでも、不親切な広告には批判が集まりがちです。
弁護士は、広告規制に違反した場合の事後的な対応についてアドバイスを行うことはもちろんのこと、事前に広告規制に違反しないかについての確認を行うことも可能です。
法律事務所Zでは、企業からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、広告規制に違反した場合のサポートはもちろん、事前チェックについてもアドバイスを行うことが可能です。
広告対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
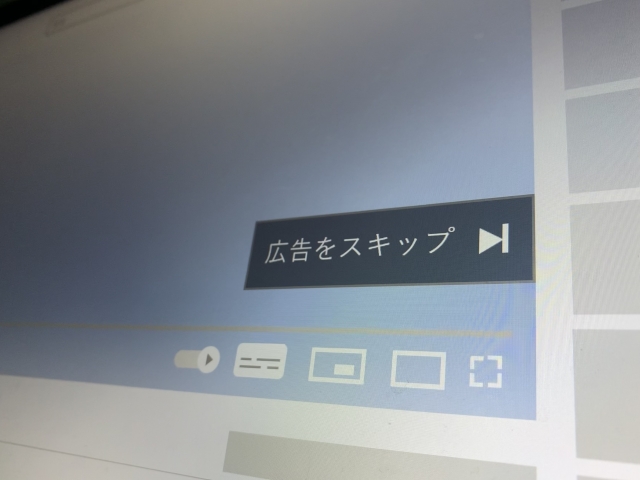
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説



