

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「クレーム対応」についてのお話です。
「こちらにも非があったかもしれないが、クレームの内容が度を越している」
「変な言いがかりをつけてくるクレーマー対応に時間がとられる」
このようなお悩みを抱えている方々は多いのではないでしょうか。
自分たちだけでクレーム対応をしようとすると労力と費用が掛かり、ストレスも溜まってしまうと思いますが、弁護士に対応を依頼すればスムーズに解決できるケースもたくさんあります。
例えば、次のような事例を考えてみましょう。
窓口対応へのクレーム
A社は電話窓口を設置しており、ユーザーからの質問などに対応をしていますが、あるユーザーから、サービスにうまくアクセスできないという問い合わせがあり、その後、電話窓口の態度が気に入らないということで、頻繁に電話が来るようになりました。
そのユーザーは電話口で「お客に向かってその態度はなんだ」、「謝れ」、「誠意を見せろ」、「上司を呼べ」、「インターネットに書き込むぞ」などといっており、何度説明しても電話をかけ続けてきます。
他の電話に対応することができなくなりますし、電話窓口の担当者も精神的に参ってしまっています。
このようなことでお困りの場合には、弁護士に相談し、あるいは弁護士から連絡をするということが有効な場合があります。
逆に、自社だけで対応しようとして抱え込んでしまうと、従業員の負担が大きくなってしまい、精神的な悪影響が出ることにもなりかねません。
クレーム対応のポイント
クレーム対応の難しさは、そもそもクレーマーが何を要求しているのかわからない、また、不当な要求であるため応じられないというところにあります。
そのような状況の中でクレーマーとやり取りをしても、クレーマーからすれば自分の要求が受け入れられずよりフラストレーションがたまりますし、会社としても応じられないということを伝えることしかできず、対応に窮することになります。
そのため、このような場合には、まずはクレーマーの要求をしっかりと確認したうえで、その背景事情についての事実確認を十分に行う必要があります。
事実確認を行うにあたっては、担当者や関係者へのヒアリングが必要になることもありますし、複雑な場合には時系列で整理することが有益であると考えられます。また、ヒアリングの内容は書面(ヒアリングメモ)として残しておくようにすることで後々証拠として利用することも可能になります。
そして、確認・整理をした事実関係を踏まえて、クレーマーの要求を法的に整理し、法律・契約上の根拠を欠く不当なものであるということを伝えることが有益です。
法律・契約の範囲外であることを明確にすることで、そのような要求には応じられないとして、要求を断ることができるのです。

クレーム対応を弁護士に依頼することのメリット
上記のポイントに従ってクレーム対応を行うとしても、クレーマーの要求が法律・契約上の根拠を有するか否かを判断するのは難しいことも多いです。
また、法律・契約上の根拠を欠く不当なものであると窓口から伝えても、クレーマーは納得しないことも多々あります。
そのような場合には、弁護士に相談することが考えられます。
弁護士は、事実確認のポイントを理解していますし、法律・契約や裁判例の調査・確認を行い、法的な分析を加えて、法律・契約上の根拠を有するかの整理をすることができます。また、必要に応じて専門家としての弁護士がクレーマーに連絡をすることで、クレームが収まることもあります。
さらに、クレームが解決したことを示す合意書・確認書を取り交わすことによって、後々の蒸し返しを防ぐことができますが、そのような合意書・確認書の作成も弁護士に依頼すればスムーズに進むと考えられます。
不幸にもクレームが収まらず裁判になってしまった場合でも、クレーム対応の早期の段階から弁護士に対応の依頼をしておくことで、事実関係を整理した一貫した態度をとることができ、また、証拠のことを常に意識した対応をしてもらうことが期待できますので、裁判上不利な状況になるのを避けることができるはずです。
特に、対応・交渉中に主張がブレてしまい、裁判でその点を指摘されると、裁判官にもよくない印象を与えかねないため、一貫した態度をとることは非常に重要であると考えております。
他方で、全てのクレーム対応を弁護士に依頼していると、費用もかさみますし、非効率となることも多いと思われます。
そのような場合には、クレームの処理体制を弁護士の関与の下で構築しておくことが有益と考えられます。クレーム処理の基本方針・判断基準や処理手順、どの範囲を超えた場合には弁護士に相談する、といったことを内部的に取り決めておくことで、効率的かつスムーズなクレーム処理が可能になることも多いでしょう。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、クレーム対応はもちろん、クレーム処理体制の構築についてもアドバイスを行うことが可能です。
クレーム対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
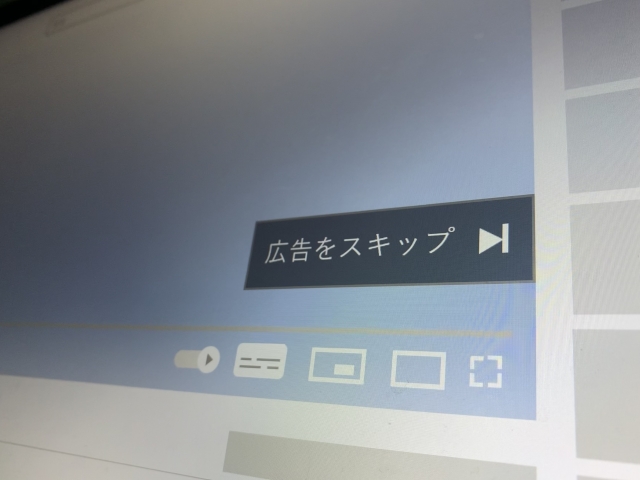
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

英文契約・国際取引とは?企業法務に精通した弁護士が解説

「トラブルが起きる前に」~中小企業が最低限整えるべき法務チェックリスト~
- 契約書作成・チェック
- クレーム対応
- 債権回収
- 労務問題

カスハラ(カスタマーハラスメント)対応とは?会社は何をすればよい?企業法務に精通した弁護士が解説
- クレーム対応
- 労務問題
- ハラスメント対応

【クレーム対応】【顧問契約】顧問先の「顧客とのトラブル」を穏便に解決
- 顧問弁護士契約
- クレーム対応
