

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「債権回収」についてのお話です。
「最近、取引先がしばしば支払いを遅延するけど、大丈夫かな?」
「商品を納入したのに、納入した商品に問題があった等、なにかと理由をつけて支払いを拒まれて困っている」
日ごろから取引を行い信頼関係が構築できていたと思っていたのに、このような態度を取られたりすると、不安に思ったり不信感が募ったりしますよね。
債権回収を有利に進めたい、債権回収に不安があるという場合、どのような対応が必要でしょうか。
例えば、次のような事例を考えてみましょう。
目次
取引先の支払遅延
A社は、月末締めで翌月15日払いという条件でB社と取引をしてきて、B社が支払いを遅延することはこれまでにありませんでした。
しかし、2カ月ほど前から、B社の支払いが数日~10日程度遅れるようになってきました。ただ、支払いが遅れているとはいえA社として困るほどの遅延ではありません。
このような場合、A社としてはどのような対応をすればよいのでしょうか。
この事例では、現時点ではA社にとって大きなダメージはないようです。
しかし、支払遅延が発生することには通常理由があるものです。そして、その理由としては資金繰りが苦しいというのが多いと思います。
つまり、A社がこのままB社と取引を継続すると、債権回収ができなくなるリスクを抱えていることにもなりかねないのです。
債権回収のポイント
平常時の情報収集が一番重要
非常時に債権回収を行うには、債権の存在を示す資料(契約書など)が必要なのはもちろん、取引先の財産は何か、また、財産はどこにあるのかという情報が必要になります。例えば、預金を押さえるならどの金融機関を使っているのかという情報が必要ですし、売掛債権を押さえるなら取引先の得意先を知っている必要があります。
しかし、このような情報は、非常時になって集めようとしてもなかなか集まりませんし、集めている間にもどんどん財産が目減りしてしまいます。
そのため、平常時の情報収集こそが一番重要です。例えば、取引を開始するにあたってヒアリングや信用調査を実施する、取引開始後も状況に変化がないかを確認することにより、取引先の状況をモニタリングすることができ、結果として有事に迅速に行動することができるのです。
また、取引先との力関係にもよりますが、契約書に規定することで取引先に一定の場合に情報提供を行うことを義務付けることも考えられます。これにより決算書等の経理情報を把握できれば、将来的に信用状況の判断を行う場合に非常に有益な情報になります。
非常時のシグナルを見逃さない
平常時の情報収集を行っていても、非常時のシグナルを見落として初動が遅くなってしまっては元も子もありません。
そのため、非常時のシグナルを見逃さないこともとても重要です。
例えば、以下のような事象が生じている場合には、取引先の信用状況を再調査することも考えられます。
- 支払猶予を依頼された
- 分割払いへの変更を依頼された
- 支払遅延が発生した
- 取引に関するよくない噂を耳にするようになった
- (これは事業拡大の可能性もあるので、一概には言えませんが)所有不動産の登記を確認したところ、新規に担保設定がなされており、新たな借入れを行ったようである
- 従業員の退社が多い
- 経理担当者と連絡がつきにくい
- 役員の表情が曇っている、いつもと様子が違う(身だしなみが乱れているなど)
列挙したうち、後半のいくつかは些細なことかもしれませんが、注意深く観察することで会社の異変をいち早く察知することができ、自社の債権回収の可能性を高めることができる可能性があります。
非常時の対応例
上記のような非常時のシグナルを察知し、調査の結果、信用に不安があることが具体的にわかってきた場合には、債権回収のためにどのように対応すればよいのでしょうか。
既存債権を回収する
まずは、既に発生している債権を適切に回収することを目指しましょう。
もし、弁済期が来ていないという場合であっても、期限の利益喪失条項に該当する事由が発生している場合には、期限の利益の喪失を主張して早期弁済を受けることを目指しましょう。
「期限の利益喪失条項」とは?
債権を回収するには、当該債権が弁済期を迎えている必要があります(期限の利益)。一般的には、弁済期が将来(翌月末など)に設定されており、それを迎えるまでは債権回収ができないことになります。しかし、それでは非常時に債権回収ができなくなりかねないので、一定の事由に該当すれば、期限の利益を失い、直ちに債権が弁済期を迎えるという条項(期限の利益喪失条項)を契約書に入れておくのです。そうすることで、平常時であれば弁済期を迎えていない債権についても回収することが可能になります。
新たな担保・保証を獲得する
次に、取引先から担保・保証を得ていないという場合には、法的倒産手続に入った場合でも、優先的地位のない債権の取扱いになってしまいます。
他方で、取引先から担保・保証を得られていれば、優先的に回収することが可能になります。
そのため、取引先から担保・保証を得られるように取引先と交渉をすることも重要です。例えば、「貴社の財政状況が芳しくないようであり、このままの条件で取引を継続するには担保・保証を入れてもらわないと難しい」、というような交渉も考えられるでしょう。
民事保全手続を利用する
以上のような任意の交渉に取引先が応じてこないという場合には、民事保全という手続を利用することが考えられます。
民事保全は、訴訟手続による解決を待っていると権利の実現ができなくなるおそれがある場合に認められ、財産の散逸を防ぐうえでは非常に有益な手続きです。
しかし、民事保全は、あくまでも一時的・暫定的なものであり後の本案訴訟が予定されていること、担保金が必要になること、また、法的倒産手続が開始されると失効・中止してしまうこと等、注意が必要な事項も多く、せっかく手続を進めたのに空振りに終わってしまうリスクもあるため、非常時に民事保全手続を利用するかはよく見極めてから判断する必要があると考えられます。
裁判による債権回収をする
取引先に資力があるにもかかわらず支払いを拒まれているという場合には、訴訟を選択することが合理的であると考えられます。
他方で、取引先に資力がない(めぼしい財産もない)という場合には、訴訟を選択しても、訴訟中に法的倒産手続が開始されてしまう等、訴訟が功を奏さないこともあり得ます。そのため、コスト倒れになる可能性も否定できません。
もっとも、例えば消滅時効中断の効果を得るために訴訟を提起することも考えられるところであり、個別具体的な状況に応じて臨機応変な対応を取る必要があります。
民事執行手続を行う
最後に、強制的に債権を回収するには、債務名義(判決など)を取得し強制執行を行う、又は、担保権を実行するという手続が必要になります。
勝訴判決を得たからといって、常に直ちに相手から債権回収ができるというわけではないので、注意が必要です。
債権回収を早期に弁護士に依頼することのメリット
以上のように、実効的な債権回収を実現するためには、取引開始時、すなわち、契約書の作成・締結の段階からしっかりと準備をしておくことが非常に重要です。
しかし、契約書の作成には法的な知識が必要になりますし、社内で完結しようとすると相応の人員・労力も必要になると考えられます。
弁護士に早期に依頼をすれば、契約書の作成段階からの関与も可能ですし、実際に問題が発生した場合にも代理人としてスムーズに交渉、内容証明の送付、各種申立等を行うことができます。また、先々を見据えて、その時点で最善の選択を検討してもらうことができるでしょう。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、債権回収について、契約書の作成段階から裁判手続まで、幅広くアドバイスを行うことが可能です。
債権回収にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
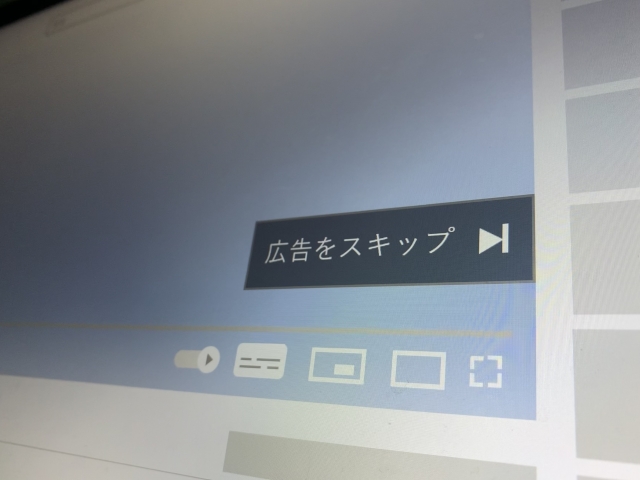
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説


