

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「誹謗中傷・風評被害」についてのお話です。
「匿名掲示板に会社の製品・サービスについての悪口が書かれている」
「SNSで会社の製品・サービスについての虚偽の情報が出回ってしまっている」
このようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
インターネットが身近になり、誰でも簡単に情報発信をすることができるようになったことの弊害として、誹謗中傷・風評被害の問題が多くなっています。
この記事では、誹謗中傷・風評被害について、対応方法を含めて解説していきます。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
事実無根であり、会社の評判が悪くなることを心配しています。
少なくとも拡散を止めたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
また、可能であれば投稿者に対して法的責任を追及したいです。
目次
誹謗中傷・風評被害の投稿を行うのはどのような人?
誹謗中傷・風評被害の投稿を行うのはどのような人が多いのでしょうか。
例えば、会社に不満を持つ従業員や、退職者がそのような投稿を行うことがあります。
このような場合には、就業規則において秘密保持義務を定め、また、会社の信用を損なうような投稿を禁止する旨を規定して退職後も効力を有することとしておく、特に退職者との関係では退職時に誓約書を取得しておくことが考えられます。
また、会社の製品・サービスを利用している顧客から、「あのサービスは●●だ」等のいわれのない悪口を書かれたりすることもあるでしょう。SNSで他の人が同調したりすると、瞬く間にその投稿が広がってしまい、収拾がつかなくなってしまうことにもなりかねません。
しかし、以上のような問題のある投稿が行われた場合、そもそも投稿者が誰かわからないのが通常でしょう。
そのため、会社としても対応に困ってしまうことがあると思います。
以下では、問題となる投稿を発見した場合にまず採るべき行動を説明して、そのあとでどのような対応が考えられるかを確認していきます。
問題となる投稿を発見したら、まずは記録化を!
問題となる投稿を発見したら、まずは、そのページを記録に残すために、スクリーンショットを取る、PDF化(PDF印刷)するなどの方法により、保存しましょう。その際、投稿番号、投稿日時、URL(https://www.XXXXXX のようなもの)も記録しておくようにしましょう。
これがあれば、弁護士に相談する際にも問題となる投稿を特定しやすいですし、投稿が削除されてしまった場合でも一定の手がかり・証拠になることがあります。
問題となる投稿を放置するリスク
問題となる投稿を放置すると、①投稿自体が削除されてしまう、②後に述べる接続プロバイダの通信記録(ログ)の保存期間が経過してしまう、といった理由により、投稿者を特定することができなくなる可能性があります。
また、いつか風評被害は収まるだろうと考えていても、インターネット上の投稿は残り続けますので、検索エンジンで検索をした人が問題のある投稿を見て会社に対するよくないイメージを持つリスクもあります。
そのため、問題となる投稿を認識したら、放置することなく、可能な限り早く採れる対応を検討するのが良いと考えます。
問題となる投稿について、どのような手段が取れるのか?
問題となる投稿について、大きく分けて、①投稿を削除したい、②投稿者を特定して損害賠償請求をしたい、と考える方が多いでしょう。
そこで、以下では、①投稿を削除する方法と、②投稿者を特定する方法について、分けて説明をします。
投稿を削除する方法について:削除請求
問題となる投稿を削除するには、(i) メールやオンラインフォームを使って行う方法と、(ii) 裁判所の手続による方法とがあります。
(i)のメールやオンラインフォームを使って行う方法は、サイト管理者やプラットフォーム運営者等に対して、削除の依頼をするという方法です。
この方法は、基本的には削除を「お願い」するものになり、削除を依頼する際の投稿内容も考慮して対応をしているものと思われますので、できる限り分かりやすく説得的な依頼にする必要があると考えられます。そして、依頼先となる管理者・運営者の属性により、どのような対応がなされるかが大きく異なるところでもあるので、「あそこが消してくれたからここも消してくれるだろう」という判断が必ずしも通用しないところでもあります。
この方法では投稿をしてもらえなかった場合に、(ii)の裁判所の手続による方法を検討することになります。
(ii)の裁判所の手続による方法は、裁判所に対して、削除仮処分命令を申し立てることにより行われるのが一般的かと思います。
削除仮処分命令の申立てが認められれば、サイト管理者・運営者は、問題の投稿を削除するケースが多いです。そのため、その後の本案訴訟である削除訴訟は行われないのが通常です。なお、削除仮処分命令を出してもらうには、供託(30万円前後)を行う必要がありますが、投稿が削除されれば、返してもらうことができるのが通常です。
他の方法として、法的な手段ではありませんが、いわゆる逆SEO対策(他のサイトの検索順位を高めることで、問題の投稿を検索結果の上位に表示しない)という方法も考えられます。
投稿者を特定する方法について:発信者情報開示
投稿者を特定する目的は、投稿者に対する損害賠償(慰謝料)請求を行うことに主眼があります。
つまり、最終的な目標は、投稿者の氏名・住所等を入手して特定することになります。
そして、問題となる投稿の投稿者を特定するには、一般に、匿名サイトでは2段階の請求が必要になります(より複数の段階が必要になることもありますが、ここでは割愛します。)。
1段階目は、サイト管理者に対するIPアドレス等の開示請求です。これは、当該サイトに投稿した人のIPアドレスを知ることを意味し、これにより2段階目の請求を行うことができるようになります。サイト管理者は、IPアドレス等の情報は持っている可能性がありますが、そのIPアドレス等を使用していた人は把握していないのです。
2段階目は、接続プロバイダに対する契約者の氏名・住所等の開示請求です。1段階目で入手したIPアドレス等の契約者が誰かを、接続プロバイダに開示するよう請求します。これにより、ようやく契約者の氏名・住所等を入手して特定することができるのです。なお、ここで判明するのは、あくまでも接続プロバイダとの契約者の情報であり、契約者と投稿者が一致するのかという問題がある(契約者≠投稿者の可能性がある)ということには注意が必要です。
1段階目は、メールやオンラインフォームにより可能なこともありますが、2段階目は基本的に裁判所での手続が必要です。
そして、裁判所の手続を利用する場合には、民事保全(仮処分)か、発信者情報開示命令を利用することが考えられます。どの方法が良いかについては、サイト管理者・運営者の属性や、プロバイダの属性等を踏まえ、事案に応じて判断することになります。
また、接続プロバイダの通信記録(ログ)は、各社の方針で保存期間が決められているので、問題となる投稿を発見したらなるべく早く行動することが重要です。
加えて、1段階目と2段階目を一体的に行える発信者情報提供命令という手続もありますが、かえって長期化するケースもあるようで、これが使い勝手が良い制度かは今後の動向を見る必要があると思います。
削除請求と発信者情報開示はどのように使い分けるのか?
削除請求は、投稿を消すものですので、拡散を防止する上では有効です。他方で、新たな投稿がなされる可能性は否定できません。
発信者情報開示は、投稿者に対する法的責任を追及するためのもので、投稿者に今後の投稿を抑止する効力が見込まれます。他方で、裁判所に認めてもらえないと、むしろ投稿者が過激化する可能性も否定できません。
このように、目的によって使い分けをする必要がありますが、いずれの方法も今後のリスクを完全に排除できない可能性があるという点には注意が必要です。
損害賠償請求について
投稿者に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求ができるほか、従業員や退職者であれば、就業規則や誓約書への違反を理由とした懲戒処分や債務不履行に基づく損害賠償請求も考えられます。
和解によって解決することが望ましい場合もありますので、弁護士に相談しながらどのような対応が良いのかを考えるのが良いでしょう。
誹謗中傷・風評被害を弁護士に依頼するメリット
誹謗中傷・風評被害は、会社に対して継続的な不利益をもたらすものです。
変なイメージがついてしまうとそれを払しょくするのはとても大変ですし、新卒で採用するような若い人たちはSNSをチェックしている人が多いと思われ、採用活動にも影響を与えることになりかねません。
弁護士は、投稿に問題があるかの法的な整理を行うことはもちろんのこと、問題があると考えられる場合の削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償について、代理人として活動することができます。
さらに、会社としてどのような対外発表をしていくかといった、危機管理的な支援をすることも可能です。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、誹謗中傷・風評被害への対応はもちろん、非常時の対応についてもアドバイスを行うことが可能です。
誹謗中傷・風評被害にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
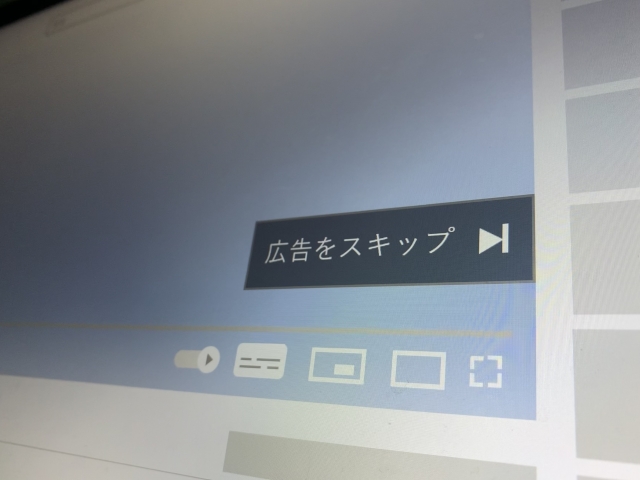
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

