

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「英文契約・国際取引」についてのお話です。
「海外の取引先との契約が英語で出てきたが、内容をどうやって確認すればいいのか?」
「国際取引で相手方がお金を支払ってくれないときはどうしたらいいのか?また、それを予防する方法はあるのか?」
このようなお悩みを抱えている事業者の方も多いのではないでしょうか。
英文契約はその用語が難解であり、理解しにくいものです。また、海外の取引先との関係で、万一お金を支払ってくれないような場合に、どのような手段をとれるかというのは難しい問題です。
この記事では、英文契約・国際取引のポイントについて解説していきます。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
先日、当社が取り扱っている商品について、海外のお客様から取引をしたいという旨の連絡がありました。日本食ブームのようです。
取引に関して、どのような内容の契約を締結すればよいのでしょうか?また、新たな取引先なのですが、気を付けるべき点はありますか?
目次
英文契約
国際的な取引においては、互いに理解が可能な言語を用いることになりますが、多く用いられるのが英語です。
そのため、国際取引といえば英文契約となるのが一般的です。
もっとも、国際取引においては、言語、宗教、伝統、習慣、法律、考え方の異なる人々との取引になりますので、誤解や紛争が生じることが多いといえます。
そのため、相手方と合意した事項についてはしっかりと契約書の内容として盛り込む必要があります。
以下では、国際取引に特有又は特に重要である問題として、準拠法及び紛争の解決方法を中心に説明を行います。
準拠法(governing law)について
国際取引においては、複数の国の法律が関係することになります。そのため、どこの国の法律に従って契約書を解釈するかを定めておく必要があります。これが準拠法(governing law)の問題です。
例えば、日本と韓国の取引を考えてみた場合に、準拠法として考えられるのは、①日本法か、②韓国法か、③それ以外の第三国の法律ということになります。
日本の会社からすれば、当然なじみのある日本法を準拠法にしたいと考えますし、韓国の会社からすれば逆に韓国法を準拠法にしたいと考えるでしょう。このような経緯で、準拠法についての意見が一致しない場合には、第三国の法律を準拠法とすることもあり得ます。
もし、準拠法が契約上定められていない場合は、どこの法律が適用されるのでしょうか。これはケースバイケースと言わざるを得ませんが、関連する国の国際私法に従い、一般的には契約当事者の意思により選択された法律、その意思が明らかでないときは、契約締結地、義務履行地、その他を考慮しながら決定されることになります。
なお、国際的な物品の売買契約については、通称CISGという条約が自動的に適用されることがあります。その適用を排除したい場合には、その旨を契約に明記しておく必要がありますので、注意が必要です。
冒頭の例でも、どの国の法律を準拠法とするかについて、契約で定めておくべきといえます。
紛争の解決方法について
日本の当事者同士の契約についての紛争であれば、日本の裁判所に提訴するというのが一般的ですが、国際的な取引になると、どのような手続により紛争を解決するのかという点でも問題が発生します。
解決を第三者の判断に委ねるという場合の選択肢としては、裁判、仲裁、調停があります。このうち、調停(mediation)については、話し合いによる解決であり、紛争当事者が調停案に従うことに同意しなければ拘束力を生じないので、終局的な解決手段としては必ずしも機能しない可能性があります。
裁判が選択されると、ある国の裁判所において紛争に関する判断がなされるということになります。基本的には、公権力による公正・正確な判断を期待できますが、国によっては自国民に有利な判決が出される可能性もあり、必ずしも公正・正確な判断を得られるわけではない可能性もあります。また、判決を得たとしても、その判決をもって外国において執行ができるのかという問題もあります。
国際的な取引においてよく採用される紛争の解決方法としては、仲裁(arbitration)があります。仲裁は、一般的に、執行を行いやすいといわれており(執行国や仲裁地の条約の締結・加盟状況、また、各条約の内容を踏まえる必要はあります。)、仲裁人を選定できるので専門家による実務を踏まえた判断が可能になり、また、手続も裁判に比べて迅速であるといわれています。
しかし、仲裁を行うためには、仲裁合意が必要になります。仲裁合意においては、①仲裁機関、②仲裁人の人数・選定方法、③準拠する仲裁規則、④仲裁地、⑤仲裁言語を定めるのが一般的です。
このような仲裁合意を紛争が起こってから行うのは極めて困難ですので、紛争解決手段として仲裁を希望する場合には、取引の開始前に必ず取り決めておく必要があります。
冒頭の例でも、紛争の解決方法について、具体的に契約で定めておくべきといえます。
その他重要な条項
以上の他にも国際取引において特に問題となるものとして、価格条件・引渡条件をどのように取り決めるかの論点(インコタームズが良く用いられます。)や、代金の支払いをいつどのように受けるかの論点(電信送金や信用状決済など)もあります。
これらについても、契約書では明確に取り決めておく必要があります。
冒頭の例では、新たな取引先とのことなので、代金の回収が困難にならないような支払条件を設定する必要があります。
英文契約の確認をおろそかにするリスク
英文契約というのは、そもそも理解が難しく、相手から提示されたものをよく確認せずにそのまま受け入れてしまうということもあるかもしれません。
しかし、取引相手は海外におり、言語・文化・慣習・歴史などの背景事情が日本とは全く異なる者を相手にすることになるので、日本国内での取引と同じように考えていると問題が発生した際に権利を適切に確保することができない可能性があります。
日本国内での取引であれば、最終的には日本の裁判所に訴えればよいと考えるかもしれませんが、国際取引だとそうもいかない可能性すらあります。
国際取引において発生した紛争を解決するというのは、国内取引におけるものに比べてコストも時間も労力もかかることになり、できる限り避けるべきといえます。
このように、英文契約の内容をしっかりと確認するということは非常に重要といえます。
英文契約対応を弁護士に依頼するメリット
上記のとおり、国際取引において発生した紛争を解決するというのは、国内取引におけるものに比べてコストも時間も労力もかかることになり、できる限り避けるべきといえます。
そのため、英文契約の内容の精査は非常に重要になりますが、社内のリソースで行うには難しい部分もあると思います。
弁護士は、契約交渉に慣れており、特に国際的な案件を多く取り扱ってきた弁護士であれば英文の契約の確認にも精通しているでしょう。
法律事務所Zでは、留学経験のある弁護士や英文契約のチェックを豊富に行ってきた弁護士が、英文契約についてのアドバイスを行うことが可能です。
英文契約対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
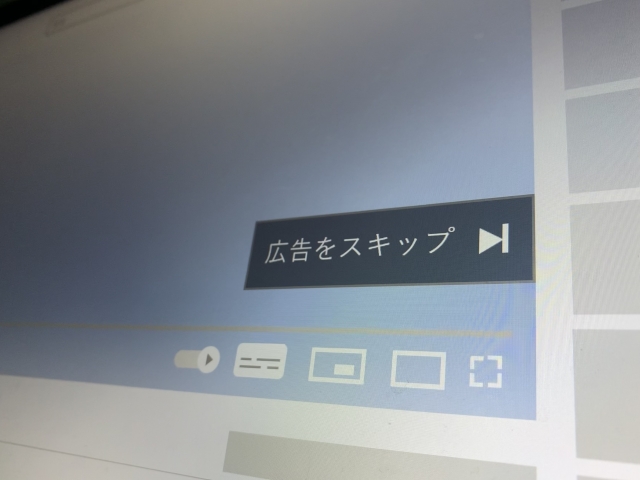
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

英文契約・国際取引とは?企業法務に精通した弁護士が解説

※開催済 オンラインセミナー:英文契約のポイント及び東南アジアへの進出の留意点
- 英文契約・国際法務

英文秘密保持契約(NDA)の解説:交渉で見逃せない3条項
- 契約書作成・チェック
- 事業承継・M&A
- 英文契約・国際法務

日本企業が海外進出する際の留意点は?企業法務に精通した弁護士が解説
- 英文契約・国際法務

Distribution Agreement(販売店契約)のポイントを企業法務に精通した弁護士が解説
- 英文契約・国際法務

【M&A・事業承継】富山県の企業と外国企業との資本業務提携案件に関するアドバイス
- M&A
- 英文契約・国際法務

【英文契約】英文契約書・合意書等の作成
- 英文契約・国際法務

【英文契約】【契約書】海外取引の契約書ひな形を作成
- 契約書作成・チェック
- 英文契約・国際法務
