

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「訴訟対応」についてのお話です。
「裁判所から郵便が届いた。どうやら従業員から訴えを提起されたようだが、どう対応すればよいのか?」
「取引先が代金を払ってくれないので訴訟を提起したい」
このようなお悩みを抱えている事業者の方も多いのではないでしょうか。
訴訟対応は裁判所との関係で細かな対応が必要になり、また、手続も詳細に決まっています。実際に訴訟が始まれば、期日への出頭も必要になります。
紛争の実態を誰よりも理解しているのは会社・事業者ですが、それを適切に裁判所に伝えることができなければ、有利に進められるはずの訴訟もうまくいかなくなってしまいます。
この記事では、訴訟対応のポイントについて解説していきます。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
先日、謄写が納入した部品について、一部不具合があったとのことで取引先から書面が届きましたが、当社の部品に問題はないと思ったので、何も連絡をしませんでした。
そうしたところ、先日訴状が届いてしまいました。
この裁判には対応する必要があるのでしょうか?
目次
訴訟対応とは?
当事者間での紛争は、まずは交渉という任意のプロセスにより解決を目指すのが一般的ですが、任意のプロセスでは解決できない場合に、裁判所の関与の下で紛争の解決を目指すことになります。
このような裁判所の関与の下での紛争解決のプロセスを一般的に訴訟と呼び、訴訟に対応することを訴訟対応といいます。
つまり、訴訟対応というのは、当事者の意見を適切に裁判所に伝え、裁判所に自己の求める判決を出してもらい、紛争を解決するためのものなのです。
具体的な内容について
訴訟対応には、大きく分けて、①書面準備、②期日対応、③尋問対応が含まれます。
以下、それぞれの内容を確認していきましょう。
書面準備
まず、裁判所に対して何かを説明する際に用いられるのは、基本的には書面です。裁判所に対して口頭で説明しようとしても、通常は「書面にまとめて提出してください」といわれてしまいます。
つまり、どんなに紛争の具体的な内容を理解していても、それを書面にまとめることができなければ意味がないのです。
そして、書面を作成するにあたっては、法律の内容を理解して、証拠も踏まえつつ、裁判官を説得できるようなものにまとめ上げる必要があります。
弁護士は、事実関係を聞き取り、それを書面にまとめ上げるという対応を日々行っていますので、会社・事業者と裁判所の橋渡し役を担うことができ、会社・事業者の主張を適切に裁判所に伝えることができます。
提出する書面の種類としては、訴状、答弁書、準備書面等があります。また、相手方から出された書面の内容を理解・分析して、書面により的確な反論を行う必要もあります。
期日対応
およそ1~2カ月に1回ほどのスパンで、裁判所において期日が開かれます。
期日の種類としては、口頭弁論期日、準備的口頭弁論期日、弁論準備手続期日、書面による準備手続等があります。それぞれの期日の種類によって行えることが異なりますが、ここでは詳細は割愛します。
期日というのは、基本的には、裁判所に提出した書面を踏まえて、裁判所から質問を受けたり、問題点について議論をしたりする場です。そのため、提出した、あるいは相手方から提出された書面の内容をよく理解し、どのような議論がなされるかを予測したうえで、期日において裁判所や相手方からの質問・議論に的確に回答することが必要になります。
この期日には、基本的には会社の代表者の方が参加しなければならず、担当者のレベルでは参加できるとしても事実上同席(傍聴)しているだけということになります。
しかし、毎回の期日に会社の代表者の方が参加するというのは現実的ではありません。この点、弁護士であれば、会社の代理人として活動することができますので、会社の代表者の方にご参加いただかなくても、弁護士が裁判所とやり取りをすることができます。
尋問期日
裁判所といえば、「証人尋問」や「本人尋問」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。
尋問が行われる期日を一般に尋問期日といいます。訴訟対応の中でも入念な準備が必要になるプロセスです。
尋問期日に先だって、陳述書という、訴訟の当事者本人や証人が紛争の経緯やその他の背景事情等についてまとめた書面を作成して、裁判所に証拠として提出することになります。
また、いざ裁判所の前で尋問を受けるとなると、本人は非常に緊張してしまいますので、尋問練習・証人テストを行うというのが一般的です。
このような準備を経て、尋問期日が行われるのです。
尋問は非常に難しいですが、弁護士を代理人につけておけば、適切に準備をして、当日も経験をベースに尋問を行うことが期待できます。
和解・判決について
概ね以上のプロセスの中で、裁判所は、当事者に対して和解を提案することが多いです。
和解の提案は、尋問よりも前に行われるか、尋問の後に行われるかというところで分かれ目があります。和解が尋問の後に行われる場合、裁判所の心証(事実関係についての内心の認識や確信)がほぼ出来上がってしまっているといわれており、裁判所からの和解提案の内容を大きく動かすのは難しいという印象があります。
他方で、和解が尋問よりも前に行われる場合、裁判所の心証は(落としどころは見えつつも)まだ固まっていない部分があり、そのため裁判所からの和解提案も柔軟な内容となり、当事者としても交渉の幅をもって議論をすることができるという印象があります。
裁判上の和解によって紛争を解決することができなければ、最終的には判決が下されることになります。
判決が下されると、敗訴した当事者は、当該判決に対して不服があるとして控訴するか否かを検討することになります。控訴期間は判決書の送達がされた日の翌日から起算して2週間とされているので、非常に短期間での判断を迫られることになります。そのため、社内でも、万一の場合に備えて、どのような対応を採るかについては十分に議論・整理をしておく必要があります。
逆に、勝訴した当事者は、強制執行をするかを検討することになります。勝訴判決を得たとしても、相手方が任意に支払等の義務履行を行わなければ、判決を得た内容を実現することはできず、強制執行を行わなければならないという点には注意が必要です。
訴訟対応をおろそかにするリスク
上記のとおり、訴訟対応というのは、裁判所を説得するプロセスです。
どんなに事案として有利であっても、それを裁判所に適切に伝えることができなければ意味がありません。
また、相手方の請求には理由がないと勝手に判断して、裁判所からの呼び出しを無視して書面の提出もせず期日を欠席した場合、欠席判決(原告勝訴の判決)を受けてしまいます。
このように、訴訟対応は決しておろそかにしてはならないのです。
訴訟対応を弁護士に依頼するメリット
訴訟は、自己の権利を実現するための最後の手段であり、裁判所の判断を仰ぎ、それに基づいて強制執行も可能になるという、非常に強力な手段です。
しかし、上記のように、法的な論点や手続きを理解したうえで適切に訴訟対応を行わなければなりませんし、敗訴した場合のリスクも大きくなります。
弁護士は、訴訟を提起したい、あるいは訴訟を提起されてしまったという紛争の段階から訴訟対応を行うのはもちろんのこと、訴訟に至らない交渉の段階で解決するためのアドバイスも可能です。
そして、訴訟には時間、労力、費用と様々なコストを伴いますので、和解により解決すべき問題については、訴訟に至る前に、できる限り和解において解決することが望ましいといえます。
法律事務所Zでは、企業からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、訴訟対応はもちろん、訴訟に至る前の交渉についてもアドバイスを行うことが可能です。
訴訟対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
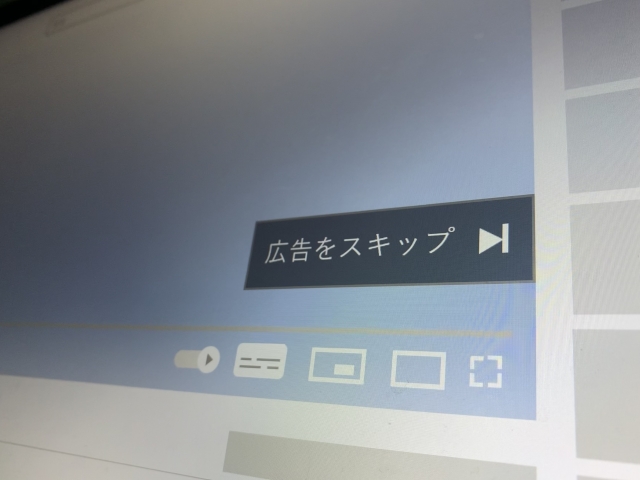
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説


