

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「不動産トラブル」についてのお話です。
「不動産を賃貸しているが、退去時にトラブルが多い」
「賃料の未払が発生してしまっている。どう対応したらよいのか」
「最近の不動産市場の盛り上がりで、賃料相場と賃料がかけ離れてきてしまっている。賃料を増額できないか?」
このようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
不動産は、漫然と所有・賃貸をしていればよいというものではなく、その後の管理も含めて収益性を考える必要があり、賃借人との関係性は非常に重要です。
この記事では、不動産トラブルについて、対応方法を含めて解説していきます。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
②オフィスを賃貸するビジネスをしているが、賃料の支払いが滞っている会社がある。以前は数日遅れで支払われることがあるという程度だったが、最近は1カ月支払いが遅れ、翌月にまとめて支払われるということもある。賃貸借契約を解除できないのか?
③賃料相場が上昇していて、現在借りてもらっている人にも賃料の増額の交渉をしたい。任意交渉で応じてくれなかったらどうしたらよいのか?
目次
退去時のトラブルについて
賃貸借契約が終了し、退去する際に一番問題になりやすいのは、原状回復費用の負担です。
原状回復費用は敷金から差し引くことができるのですが、その金額や範囲を巡って問題になるのです。
これについては、国土交通省により「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「原状回復ガイドライン」)が取りまとめられています。
原状回復ガイドラインの考え方
原状回復ガイドラインは、原状回復について、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
そして、建物価値の減少について、3つにブレークダウンし、それぞれについての修繕等の費用の負担者を以下のように整理しています。
| 区分 | 負担者 | |
|---|---|---|
| A | 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの | 賃貸人 |
| B | 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とはいえないもの) | 賃借人 |
| A(+B) | 基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの | 賃借人 |
| A(+G) | 建物価値の減少の区分としてはAに該当するものの、建物価値を増大させる要素が含まれているもの | 賃貸人 |
もっとも、このような区分はあくまでも一般的な事例を想定したものであり、個別具体的な事例では区分や負担者について分類に微妙な判断を求められることもあります。
賃借人は全額を負担するのか?
ある原状回復費用について負担者が賃借人であるとされる場合であっても、賃借人が全額を負担するとは限りません。設備等については、経過年数に応じて価値が変化すると考えられるからです。
例えば、カーペットについては、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を描いて、経過年数により賃借人の負担が決定されます。
もっとも、実際にある設備等が導入されて何年たっているかは、全てを把握しておくことは難しいことがあります。例えば、賃借人はいつクロスが張り替えられたのかはわからないことが多いでしょうし、賃貸人としてもすべてを把握しているかというとそうでもないことが多いと思います。
そのため、原状回復ガイドラインでは、入居年数で経過年数のグラフを代替するということにしています。入居時点での価値をどの程度にするかという点は、契約時に協議するのが適当とされています。
汚損は一部の場合 – クロスの張替えは全面してもよい?
例えば、クロスの一部が破れている場合に、その部屋全体のクロスを張り替えて、賃借人に費用を負担させるのは適当でしょうか。
これは、一部のクロスの張替えが可能なのか、その出来上がりは自然なのかなどを踏まえながら、どの範囲でクロスの張替えが必要であるかを考慮する必要があります。
その上で、賃借人に負担させるべき範囲を考えることになります(原状回復ガイドラインでは、m²単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむを得ないとされています。)。
このように、一部が汚損していることにかこつけて、賃借人に過大な負担をさせることはできないことに注意が必要です。
冒頭の事例①について
冒頭の事例では、DIYによる影響がどの程度によると考えられます。例えば、床にシートを張ってはがしたときにべたべたになってしまったような場合は「B」に該当することもあるでしょう。また、棚を増設する際に穴をあけることがあるかもしれませんが、その穴がピン等による小さなものであれば、通常の損耗と考えられて「A」に該当することもあるでしょう。 個別具体的な判断にはなりますが、状況をしっかりと確認して判断することが重要です。
賃料不払いへの対応について
賃料の不払いは、発生する都度解決するようにしなければなりません。不払いの賃料が積み重なっていくと、到底支払えない金額になっていくからです。
それでは、賃料の不払いが数カ月続いたような場合はどうでしょうか。
当然ですが、賃料の不払いは賃借人の債務不履行になりますので、賃料を支払ってくれない賃借人との間の契約は解除したいと考えると思います。
しかし、賃貸借契約は、いわゆる継続的契約として、信頼関係が破壊されていなければ解除が認められないという考え方が判例上確立しています。
こちらの解除権行使に賃借人が応じてくれればよいですが、応じてくれない場合には裁判所の判断を仰ぐ必要があります。そのため、信頼関係が破壊されたといえるのはいつからかという問題が出てくるのですが、これは個別の事情により判断せざるを得ません。
信頼関係が破壊されるのは、一般的には、賃料の不払いだと3カ月くらいといわれているようですので、賃料の不払いが2カ月しかない場合には、その他の事情も含めて信頼関係の破壊があると主張していく必要があることになります。
冒頭の事例②については、判断が難しいところですが、賃料滞納の回数や交渉の経緯、相手方の態度を踏まえて、信頼関係が破壊されたといえるかを慎重に判断することになるでしょう。
なお、賃料も払えない賃借人は、その他にも負債を抱えていることが多く、破産手続が開始されることも少なくありません。
破産手続に入っていった場合には、破産管財人が登場し、管財人が賃貸借契約について終了するか継続するかの判断をすることになります。
賃貸借契約を終了する場合は、物件が明け渡されることになりますし、賃貸借契約を継続する場合には、破産管財人から賃料の支払いを受けることになります。
破産手続が始まったからといって、直ちに明渡しを請求することができるわけではないという点に注意してください。
賃料増額の方法について
私的自治の下、賃貸借契約における賃料は当事者の合意によって定められます。そして、契約期間中は、賃料は一方当事者の希望で変更できないのが原則です。
もっとも、賃貸借契約は長期にわたることも多く、物価の上昇、開発の進行など、社会情勢の変化によって、合意によって定められた賃料が相場に照らして不適当になってしまうことがあります。
そのため、借地借家法では、賃料の増額・減額を請求する権利が定められています(借地借家法11条、32条)。
以下、具体的に見ていきましょう。なお、以下では、建物の賃貸借についての解説をすることといたします。
どのような場合に賃料の増減を請求できる?
建物の賃料の増減を請求する要件は、借地借家法32条1項が規定しています。
具体的には、建物の賃料が不相当となったときには、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができるとされており、不相当の要因として、以下の判断要素が例示されています。なお、いずれも例示であるため、他の要素が考慮されることもあります。
①土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減
②土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動
③近傍同種の建物の借賃との比較
上記①は、具体的には、必要諸経費(建物に係る減価償却費、維持修繕費、公租公課、損害保険料など)のほか、賃貸借管理費や空室等損失相当額も含まれることがあります。
なお、一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、当該期間は賃料増額を請求することができなくなるので、注意が必要です。
賃料の増減を請求したが、相手が応じてくれないときは?
賃料の増減を請求して任意に交渉したものの、相手が賃料の具体的な金額(「相当額」)に納得してくれない場合、具体的な金額は調停又は裁判により決定されることになります。
ここで注意が必要なのは、法的手続として、まずは調停を選択しなければならないということです。賃料増減に関する訴えを提起しようとするときは、原則としてまずは調停の申立てをしなければならないとされているのです。
調停は、基本的に話合いによる解決であり、調停では解決しなかった場合に、ようやく裁判所に訴えを提起することができるとされています。
調停は、調停委員会により行われ、調停委員会は、調停主任(裁判官)1名及び民事調停委員(不動産鑑定士等の専門家)2名以上で構成されます。
賃貸借関係は賃料増減の可否に関わらず今後も続くことが想定されることや、不動産の専門家を交えた話し合いが可能ということも踏まえると、まずは調停による解決を目指さなければならないということにも合理性があるといえるでしょう。
冒頭の事例③について
賃料増額について、任意の交渉がまとまらなければ、調停を申し立てて、それでも解決に至らなければ訴訟に進むということになります。
不動産トラブルを弁護士に依頼するメリット
不動産トラブルは、慣れている会社であれば自分たちで対応できることも多いと思います。 弁護士に依頼するようなトラブルは、相手方との交渉が難航している、契約書が通常と異なる取り決めになっている、紛争にまで発展することがほぼ確実に見込まれる、というようなものになっていくと思います。
弁護士は、法的な知識をベースに、新たな問題に対しても思考力を発揮して解決方法を模索することができます。また、交渉・紛争についても代理人として関与ができます。
そのため、通常の処理から外れそうな事案だなと感じた、あるいは、揉めそうだなと思ったら、早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、不動産トラブルへの事後的な対応はもちろん、契約書の内容などの予防についてもアドバイスを行うことが可能です。
不動産トラブルにお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
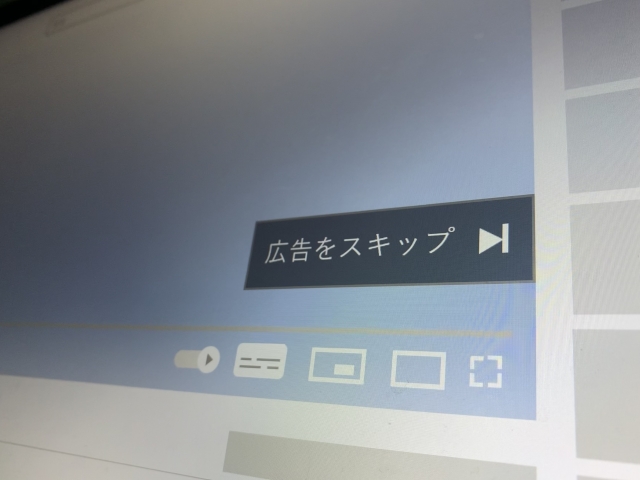
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

