

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「事業承継」についてのお話です。
「会社の後継ぎがいないので、信頼できる人に会社を継いでもらいたい。でも、まず何から始めればいいのだろう?事業承継ってどうやってやるのだろう?」
このようなお悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
人生には限りがあります。しかし、会社やビジネスはそうとも限らず、従業員、取引先など、多くの人の関与の下で成り立っており、経営者の人生の長さとは必ずしもリンクしないものです。
そうしたなかで、様々な関係者のことを思い、引き続きどなたかに会社を継いでもらいたいと考えるのは自然なことで、また、周囲に配慮ができており素晴らしいことだと思います。
この記事では、事業承継のポイントについて解説していきます。なお、中小企業庁が策定した「事業承継ガイドライン」もありますので、興味のある方はご確認してみてください。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
株主は、代表取締役のB社長と、その配偶者のCさんです。
B社長が創業以来会社を大きくしてきて、従業員も数十人規模になりましたが、B社長が高齢になってきたこともあり、そろそろ引退したいと思っています。
会社の業績は好調ですが、親族内に後を継いでくれる人はおらず、どうしたものかと頭を悩ませています。
目次
事業承継とは?どのような方法があるのか?
そもそも、事業承継とはどのようなものなのでしょうか。
実は、事業承継というのは法律上の用語ではなく、事業を承継させることを広く一般に指す言葉として用いられています。
それでは、事業承継はどのような方法によって達成されるのでしょうか。代表的な例を見ていきましょう。
株式譲渡
一番オーソドックスな方法は、株式譲渡です。株主が、会社の株式を、事業を承継してくれる人に譲渡して、会社の支配権を譲り渡すという方法です。
この方法の場合、会社の法人格(ハコ)は変わらず、そのままの状態で会社を渡すことができます。
しかし、会社には不採算部門があったりして、事業を承継したい人がその部門は必要ないと考えることもあります。そのような場合には、株式譲渡という方法は必ずしもマッチしないことがあります。
事業譲渡
次に、事業譲渡という方法があります。一つの会社が複数の事業を営んでいることもあり、例えば、製造業を行っている会社でも、他に小売業を行っていることがあったりします。そして、本業の製造業は順調だが、小売業は赤字になってしまっているということもあります。
そのような場合、事業を承継したい人は、本業の製造業だけを承継したいと考えることが多いでしょう。
そうしたニーズにこたえるのが、事業譲渡の方法です。事業譲渡は、簡単に言えば事業を切り出して譲渡するという方法ですので、製造業部分だけを切り出して譲渡することが可能になるのです。
なお、赤字事業を残す場合には、その赤字事業の後始末は必要になります。赤字事業に従事している人をどうするか、また、赤字事業部分に残された債権者をどのように保護するのかという問題が生じます。そのため、事業譲渡の方法も万能ではないという点には注意が必要です。
その他方法
以上の他に、会社分割等も事業承継の方法として用いられることがあると思います。事業譲渡とよく似た手続ですが、法的効果や手続的な違いがあります。詳細はここでは割愛します。
どの手法が望ましいかという点については、法務的な観点の他に税務的なメリットを受けられるかというところも大きな検討材料になってきますので、多角的な視点での検討が必要になります。
冒頭の事例だと、業績は好調とのことなので、通常の株式譲渡でも事業承継先は見つけられる可能性がありそうです。
誰に事業を承継してもらうの?事業承継の相手方は?
事業承継には、当然ながら事業を承継してくれる相手が必要です。
その相手としては、主に3つの類型が考えられます。
親族への承継
1つ目は、親族です。現経営者の子をはじめとした親族に承継させる方法で、日本においては昔から広く受け入れられてきた方式ですので、関係者からは心情的に受け入れられやすいといわれています。また、後継者の育成という観点からは、早期に着手しやすいところもメリットであるといわれています。
他方で、最近は「家業を継ぐ」という選択がとられないこともあります。継ぐ側からしても、自分の職業は自分で決めたいという思いが強くあるでしょうから、家業を継いでほしいと思う場合には、継ぐことに魅力を感じてもらえるような事業にしておくことが非常に重要になります。
親族以外の役員・従業員への承継
2つ目は、親族以外の役員・従業員です。会社の経営には親族以外の人も関与しているのが通常であり、そのような人たちも会社に対しては強い思い入れがあることも多いでしょう。そのような方々であれば、会社を適切に発展させていってくれるという期待ができます。
役員・従業員に対して株式を渡す場合には、役員・従業員が株式を買い取る資金を持っているかという点が問題になりますが、役員・従業員持株会を利用する方法もありますので、どのような方法が適切かは個別に検討する必要があります。
他方で、複数の親族が株式を保有している状況では、役員・従業員が事業を承継するということについて、十分に理解していただく必要も出てきます。株式を譲渡したくないという親族が出てくるかもしれませんし、手厚い説得・調整が必要になることも多いです。
社外の第三者への承継
3つ目は、社外の第三者です。会社が魅力的な存在であれば、社外の第三者が事業を引き継ぐことを希望することもあります。 社外の第三者との調整になりますので、従業員や取引先に知られないように特に秘密裡に行う必要があります。また、買手もじっくりと会社の良し悪しを判断したいと考えるのが通常ですので、多くの資料を提供する必要があり、また、質問事項にも適切に回答する必要があります。
このように、一定の負担はかかりますが、安心して任せられる社外の第三者が見つかれば、株式の譲渡対価を受け取ることができるという点も、現在の株主にとっては大きなメリットといえるでしょう(他の方法でも対価は通常受け取れると考えられますが、既存の関係性や事業を承継してもらうという側面もあるので、株主として納得のいく価格になるかという問題は出てくるでしょう。)。
冒頭の事例では、親族で承継してくれる方がいないようなので、役員・従業員や社外の第三者から事業承継をしてくれる人を探す必要があります。
事業承継を行う準備は?
事業承継を行うにあたって必要な準備はどのようなものがあるのでしょうか。
まず考えられるのは、会社の状況の整理です。会社を引き継いでもらうのですから、引き継いでもらえる人に対してどのような会社であるかを十分理解していただく必要があります。とても重要なポイントとして考えられるのは以下のとおりです。
- 株主は誰か。株券を発行しなければならない会社の場合、株券は発行しているか。
- どのような資産があるのか、どのような負債(借入)があるのか。
- どことどのような取引を行っていて、それぞれについて契約書はあるか。
- 労務関連の規程は整っているか。従業員との関係性はどうか。問題は生じていないか。
- 保有又は利用している知的財産権がある場合、権利関係はきちんとしているか。
- 訴訟や紛争がないか。
- 税務申告はしっかりしているか。
- 会計上問題のある処理はしていないか。
これらについては、日ごろから資料を整理しておくことですぐに対応できることもあるので、そのような整理を行うこと自体が、実は事業承継を行う準備になっています。
また、以上の他に、経営的な側面で問題がないかという点も説明できるようにしておく必要があります。
もし、このような整理を行う上で問題が発見されたとしても、直ちに会社を引き継いでもらえないということにはなりません。
問題をしっかりと把握し、採り得る対応策をとっていくことで、引き継いでもらえる会社になっていくということも重要です。
ですので、問題が発見されたからといって隠すのではなく、正面から向き合っていくことがとても大切と考えます。
また、引き継いでもらえる相手を選定するという作業も重要です。親族や社内の方であれば個人的な関係から選定ができると思いますが、社外の第三者からも候補者を探すということになれば、仲介業務を行っているところを利用することも考えなくてはなりません。
仲介業務を依頼するとそれなりの費用が掛かりますので、どのような業務をしてもらえるのか、どのタイミングでいくらのお金を支払う必要があるのかというポイントはしっかりと確認して契約を締結しなければなりません。
なお、借入を行っている場合には、金融機関との相談も必要になってきます。経営者保証として代表者が連帯保証人となっていることもあるでしょうから、その処理(連帯保証人から外れること)を相談して、買手候補にもその内容を伝えておく必要があります。
事業承継に必要な契約書は?内容のポイントは?
株式譲渡による事業承継の場合、株式譲渡契約書を締結するのが一般的です。 内容としては、①株式の対価、②対価の支払時期・方法といった通常の売買契約で定められるような事項に加えて、③誓約事項(一定の事項に対応することを約束(誓約)するもの)、④表明保証(会社の状態はこういうものですよと表明し保証するもの)、⑤補償条項(何らかの違反が起きた場合にお金を支払いますというもの)が盛り込まれるのが通常です。
例えば、④表明保証について、広く表明保証を求められると思ってもいなかったところで表明保証の違反が生じる可能性がありますし、⑤補償条項については、(i) 責任額に条件を設けるか、(ii) 責任を負う期間に制限を設けるかといった点は重要な交渉ポイントになります。
これらについては、非常に複雑な内容を含むものであり、売主である株主の金銭的な負担に直結するものので、詳しい弁護士を自ら選んで相談することをお勧めいたします。
なお、株主ではなくなっても、業務の引継ぎや従業員との関係性の維持のために会社に残ってほしいと求められることもあります。その場合には、経営委任契約を締結することもありますので、その内容の交渉も必要になります。
事業承継対応を後回しにするリスク
事業承継対応を後回しにするとどのようなリスクがあるでしょうか。
まず、事業承継には時間がかかります。数年間かかることもありますし、そう簡単に物事が進んでいくわけでもありません。
現経営者の方もどんどん歳を取っていきますし、いつまで健康かもわかりません。
あまり考えたくはないですが、突然病に倒れ亡くなってしまうと、相続が発生することになり、株式が複数人に分散してしまう可能性もあります。
そうすると、適切な事業承継を行うことがより困難になっていきます。
このような事態に陥るのを避けるためにも、現経営者の方が健康なうちから、事業承継について検討を進めるのが望ましいです。
また、相続税の対策と絡めながら事業承継ができることもありますし、万一の事態が発生した場合に備えて事業承継に影響が出にくいような相続対策を行うことも検討ができます。
事業承継対応を弁護士に依頼するメリット
事業承継は、大きな決断です。
これで正しいのだろうか、本当に適切な相手なのだろうかと、いろいろと気を揉むことも多いでしょう。
弁護士は、事業承継に必要な契約・手続の法的サポートを行うことはもちろんのこと、様々な事例を通じて得た経験を踏まえ幅広い相談に応じることも可能です。
事業承継に向けた準備を整えていきたいが、どのようにしてよいかわからないという場合のご相談にも対応可能です。
法律事務所Zでは、事業承継を望むオーナー様や、事業承継の承継主(買手)様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、契約・手続のサポートはもちろん、事業承継に向けた準備についてもアドバイスを行うことが可能です。
事業承継にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
お問い合わせ
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
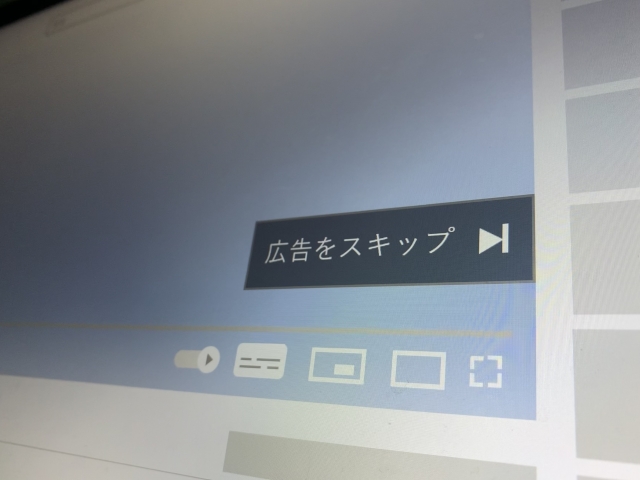
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

英文契約・国際取引とは?企業法務に精通した弁護士が解説

株式譲渡と事業譲渡、何が違う?企業法務に精通した弁護士が解説
- 事業承継・M&A

事業承継の契約書はどうしたらいい?企業法務に精通した弁護士が解説
- 事業承継・M&A

英文秘密保持契約(NDA)の解説:交渉で見逃せない3条項
- 契約書作成・チェック
- 事業承継・M&A
- 英文契約・国際法務

事業承継で “揉めないために” 早めに準備すべき法務事項
- 事業承継・M&A

株式譲渡契約(SPA)とは?株式譲渡契約(SPA)の内容やポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説!
- 契約書作成・チェック
- 事業承継・M&A

【M&A・事業承継】株式譲渡契約書を迅速にレビュー
- 顧問弁護士契約
- M&A
- 契約書作成・チェック
- 事業承継

【M&A・事業承継】石川県内の企業の買収にアドバイスした事例
- M&A
- 契約書作成・チェック
- 事業承継
