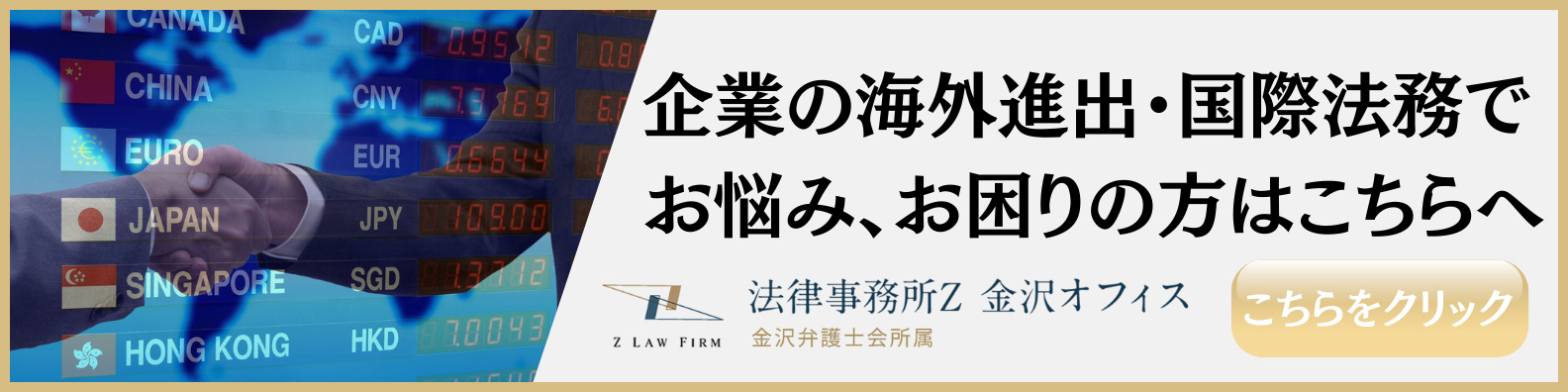こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「海外進出」についてのお話です。
「当社の製品は海外でも売れると思うので、海外進出したいが、どのような方法があるのか?」
「現地のパートナーを見つけたが、どのような契約を締結すればいいのか?」
「海外の製造拠点を作りたいが、どうすればよいのか?」
このようなことでお悩みの経営者の方もいらっしゃると思います。
海外には大きな市場が広がっており、適切な現地パートナーと連携することで大きな収益を生み出す可能性を秘めています。
他方で、どのような形で海外進出ができるのか、また、法的なリスクはどのように回避すればよいのかなど、海外進出にあたってはご不安な点も多いと思います。
この記事では、日本企業の海外進出のポイントについて解説していきます。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
|
当社は、食品を取り扱う会社です。
先日、当社が取り扱っている商品について、海外のお客様から取引をしたいという旨の連絡がありました。日本食ブームのようです。
これを機に、海外にも当社の商品を展開していきたいと思っているのですが、どのような方法があるでしょうか?
|
海外への進出形態
海外への進出形態は様々です。
代表的な例として、
①販売店・代理店の選定による進出
②駐在所による進出
③支店による進出
④法人設立による進出
が考えられます。
以下、それぞれについて解説します。
販売店・代理店の選定による進出
販売店・代理店の選定による進出の場合には、自社が直接海外に進出するのではなく、信頼できる現地パートナーを探し、現地パートナーに商品を流通してもらうということになります。
この場合に締結すべきは販売店・代理店契約(Distribution Agreement)です。これについては、こちらの記事をご参照ください。
この方法は、自ら拠点を構えなくてもよく、また、ある程度販売店・代理店に任せることができるというメリットがあります。
他方で、当然ですが販売店・代理店に一定の金銭を支払うことになるので利益率が下がることが想定され、また、販売店・代理店のコントロールを適切に行わなければならないという点が留意点になります。
駐在所による進出
駐在所による進出の場合、支店とは言えないレベルの小さな事務所を構えるというイメージが近いと思います。まずは海外進出の足掛かりをつかむために人を送り込むイメージです。
法的には日本本社の一部として存在することになると考えられますが、駐在所の設置には現地の法規制に従って現地政府などの許認可が必要になる場合がありますので、チェックが必要です。
支店による進出
駐在所から少し進んで支店による進出も考えられます。
支店も日本本社の一部と考えられますので、現地の法規制に従って支店を置くことの許認可を得る必要がないか、チェックを行う必要があります。
法人設立による進出
現地に法人を設立することによる進出もあります。
この場合、現地法に従った法人設立の手続が必要になりますし、国によっては外資規制により現地の人が取締役や株主にならなければならないという制限が存在することがありますので、注意が必要です。
また、現地に法人を設立するといっても、自社単独で設立する場合と、現地のパートナーとともに設立する場合が考えられます。
現地のパートナーとともに設立するメリットは、外資規制をクリアすることができることや、現地の実情に詳しいパートナーがいることでビジネスを行いやすくなるということが挙げられます。この場合、合弁契約(Joint Venture Agreement:JVA)を締結して、お互いの役割や会社の運営方針(ガバナンス)などについて取り決めを行うことになります。
さらに、現地に法人を設立するということは、現地の法人が各種取引・契約の主体となるということです。例えば労働契約をはじめ、売買契約、業務委託契約、賃貸借契約等、様々な契約書を締結しなければならず、また、その準拠法は基本的に当該国になることが多いと考えられます。ですので、現地のリーガルアドバイザーを起用しなければならないことも出てくると思われますが、海外弁護士とのコネクションがある弁護士に紹介してもらうのが良いでしょう。当事務所は、豊富な海外弁護士とのコネクションを有しております。
加えて、現地法人に勝手なことをされないように、しっかりと管理・監督する必要があります。
現地パートナーがいる場合でも、情報収集は欠かさず行う必要がありますし、重要な判断を行う際には自社の承諾を得なければならないということにしておくことが重要です。このような内容を合弁契約(JVA)において定めていくことになります。
なお、合弁契約(JVA)を締結する場合は英語で締結することが基本だと思われますので、英文契約に長けた弁護士を選定する必要があります。

どの形態の海外進出が適切なのか?
上記のように、海外への進出形態は様々ありますが、どの形態を選択するかは自社の海外進出の目的を踏まえて決定する必要があります。
例えば、「自ら海外に進出して商品を展開するというよりは、信頼できるパートナーに商品を展開してもらいたい」と考えるなら販売店・代理店の形態が良いでしょう。
他方、「どんどん海外に出て行って自ら販路を拡大していきたい」という会社の場合には、駐在所から始めて法人での進出を目指すということが適切かもしれません。
また、上記のとおり、法人としての進出は管理・監督を含めて相応のコストも発生しますので、自社の目的との関係で負担できるコストであるのかという観点からの検討も必要になります。
海外進出におけるよくある法的リスクと回避方法
海外進出にあたってよくあるリスクやその回避方法も確認しておきましょう。
代金回収
海外との取引で最も典型的なのは代金回収です。
商品を納めたのに代金が支払われないという場合、任意の交渉に応じてくれなければ強制的に取り立てるのは非常に難しい(あるいは非常にコストがかかる)ということになりかねません。
そのため、可能な限り代金は前払いにする、あるいは信用状を利用するなど、代金を回収できないリスクを可能な限り下げる方法をとっていく必要があり、その旨をしっかりと契約書に記載しておかなければなりません。
製品不良
海外から仕入れる商品に不良があったというのもよくある問題です。
海外で商品を製造する拠点を作るという場合を想定すると、日本国外での売買が行われるということになり、商品に不良があるかのチェックが適切に行えるかということも問題になりますし、仮に不良があった場合に仕入先は適切に対応してくれるのかという問題にもなります。
取引先によっては、直ちに指摘しなければ「納入したものに不備はなかった」とか「以前から同じ品質のものを納入しているので問題ないだろう」というような主張をしてくることもあり得ますので、納得のいかないものを見つけたら必ず取引先に連絡するようにすべきです。
このような事態を避けるために、契約書において、品質の基準を定めておき、検収のタイミングはいつまでとするのか、契約不適合責任の期間(品質の保証期間)や発見した場合の手続きなども取り決めておく必要があります。
現地パートナーとのトラブル
現地パートナーを選ぶのは重要ですが、信頼できる先でなければ勝手な行動をされかえって損害を被る可能性もあります。
例えば、現地パートナーが勝手に会社の商号を使って不当な広告をする、価格を非常に安くして流通させるなど問題のある販売方法を行うということもあり得ます。
また、一緒に会社を設立した現地パートナーが日本側の意向を無視してビジネスを進めてしまう、あるいはビジネスを行わなくなってしまう(自らの役割を放棄してしまう)ということもあり得ます。
このような状況に陥らないように、販売店・代理店契約(Distribution Agreement)や合弁契約書(JVA)において適切な取り決めを行うことが必要になります。また、法人を設立する場合には、日本側の人員を現地に送り込むことで直接的に監視・監督していくということも必要になります(人員を送り込むということも、合弁契約(JVA)で定めることができます。)。
契約書の重要性
海外との取引においては、特に契約書の作成が重要になります。
こちらの記事をご参照いただければと思いますが、そもそも契約書を締結していなければ何をベースに物事を考えてよいかの出発点がないことになります。
契約書があれば、そこをベースに交渉を展開することが可能になりますが、契約書がないと交渉のスタートラインすら確定できないことになってしまうのです。
また、よっぽど規範意識の低い相手方でなければ、契約書があれば相応の対応をしてくれることも期待できますので、その意味でも契約書を作成しておくことは非常に重要です。
海外進出は当事務所にご相談を
海外進出は大きなチャンスである一方、大きなリスクも生み出しかねないものです。
また、英文契約がどうしても登場してくるので、専門的な知識が必要です。また、インコタームズについての定めが必要になることも多く、日本の契約を単に英訳するだけでは足りない部分もあります。
一定のコストはかかってしまいますが、最初にしっかりとした土台を作って海外進出をすることで、結果的にその後のリスク・コストを下げることにつながります。
ここをおろそかにすると、最悪の場合、せっかく海外に設立した拠点が全く機能しなくなってしまうということにもなりかねません。
私は、海外留学の経験があり、また、これまでの業務において英文契約や海外進出のサポートを行ってきた経験があります。
そのほかにも、法律事務所Zには、外資系インハウス経験のある弁護士や四大法律事務所出身の弁護士など、様々な知見を持つ弁護士が集結しています。
海外進出をお考えであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。

 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |