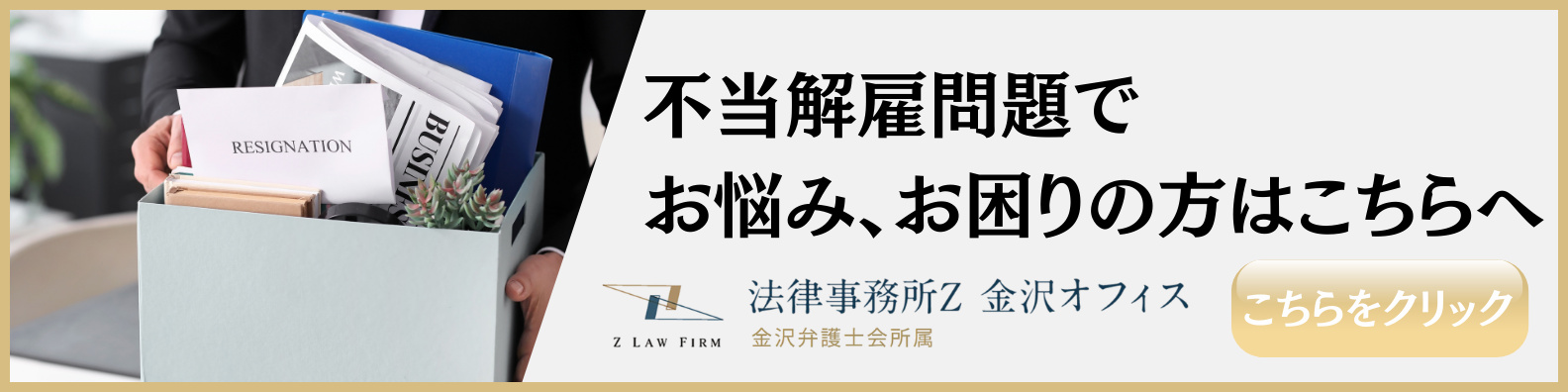こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「不当解雇」についてのお話です。
「問題社員を解雇したら不当解雇だと言われた。どう対応すればいいのか?」
「不当解雇だった場合に会社はどのような責任を負うのか?」
このようなお悩みを抱えている会社は多いのではないでしょうか。
問題社員を解雇したいと考える企業は多いですが、実際に解雇ができる場面というのはそう多くはありません。
そして、解雇ができないような事案で解雇してしまう、また、解雇にあたっての手続きを間違えてしまうと、会社は多額の金銭の支払いを命じられる可能性があり、非常に大きな問題になります。
この記事では、不当解雇にならないように注意すべき点や対策方法を解説します。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
|
当社では即戦力として採用した営業部員A社員がいます。
A社員は、期待していたような能力に達しておらず、職責を全うできていないと考えています。
そのため、A社員を解雇したいと考えているのですが、不当解雇にならないでしょうか?
|
解雇・退職勧奨についてはこちら
不当解雇とは?解雇の有効性はどう判断される?
まず、不当解雇というのは、一般に、合理的な理由がない、あるいは相当性がないような、法的に無効になる解雇をいうことが多いです。
そして、不当解雇と判断されると、労働契約が解雇時から継続していたと考えられ、会社はその間支払っていなかった賃金を支払わなければならなくなります。
これは、会社にとっては大きな金銭的損失になります。
それでは、どのような解雇が無効になるのでしょうか。
解雇の有効性は、労働契約第16条により判断されます。
具体的には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
このように、解雇が有効であるための要件は、①客観的合理的理由があり、かつ、②社会通念上相当であること、になります。
逆に言えば、これらが備わっていない解雇は、不当解雇になります。
- 解雇に客観的合理的理由があること
解雇の客観的・合理的な理由の判断にあたっては、以下の要素が考慮されます。
- 解雇事由の存在・重大性
- 労働者の改善見込みの程度
- 解雇回避措置の有無
例えば、冒頭の例では、中途採用の社員の能力不足をもって解雇することができるか、という問題になります。
一般に、中途社員は新卒社員と比べて解雇しやすいと言われます。しかし、もし裁判になれば、会社は「能力不足」を客観的な証拠をもって示さなければなりません。
そのため、会社として、A社員がなぜ「能力不足」といえるのかの資料を整えておく必要があります。例えば、①入社時に求めていたレベルに達していないこと(資格を取得していない、基本的な知識を欠くなど)を示す資料や、②一定の目標を提示していたがその目標を達成できなかったことを示す資料が考えられます。このような資料もなく、一方的に「能力不足だ」と会社が主張しても、裁判所を説得するのは困難ですので、能力不足の解雇を検討している場合には弁護士に相談すべきです。
その際、PIP(Performance Improvement Plan)といわれる制度を導入することも考えられますが、詳細は後ほど説明します。
解雇が社会通念上相当であるかの判断にあたっては、以下の要素が考慮されます。
- 使用者による不法な動機・目的の有無
- 労働者の情状
- 他の労働者との取扱いの均衡
- 使用者の対応・落ち度
- 手続きの不履践
このように、社会通念上相当であるといえるかの判断においては、他の労働者との取扱いの均衡(つまり、社内の前例との比較など)や、手続きをしっかりと行ったかというところも見られるので、感情的な解雇は慎まなければなりません。

主な解雇の理由
解雇の理由としては、主に以下のものが考えられます。
- 病気・負傷を理由とする解雇
- 能力不足を理由とする解雇
- 同僚・上司との不和(コミュニケーション能力欠如)を理由とする解雇
- 勤務態度不良や業務上のミスを理由とする解雇
- 非違行為を理由とする解雇
それぞれについて、例を挙げていきます。
病気・負傷を理由とする解雇の例
精神病により労働能力を喪失してしまったような場合が考えられます。
なお、この場合でも、(a)病気・負傷の存在が労働能力に与える影響の大きさ、(b)病気・負傷の回復の可能性、(c)他の業務等への配転の可能性等を踏まえて、解雇に客観的合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかの判断が入ります。
また、会社によっては私傷病休職の制度を導入しているところもあると思いますので、その適用についても整理をしておく必要があります。
職種の限定がない従業員が怪我をして障害を持つことになった場合でも、その障害の影響を受けない職種があるのであれば配置転換をする必要があり、それをしない場合には不当解雇になることがありますので、注意しましょう。
能力不足を理由とする解雇の例
指示した業務ができず支障が出ている、指導・教育をしても改善しない、職種や地位を特定して採用したが水準に達していない、報・連・相がないというような場合が考えられます。
この類型では、解雇に客観的合理的な理由があり、社会通念上相当といえるかの判断では、一般的に、(a)労働契約上、その労働者に要求される職務の能力・勤務態度がどの程度か、(b)勤務成績、勤務態度の不良はどの程度か、(c)指導による改善の余地があるか、(d)他の労働者との取扱いに不均衡はないか等について検討することになると考えられます。
なお、中途採用者は、新卒採用者と比較すると解雇が認められやすい傾向があります。
後で説明しますが、能力不足での解雇をする場合には、能力不足を示す証拠が必要になりますので、注意してください。
同僚・上司との不和(コミュニケーション能力欠如)を理由とする解雇の例
自己のやり方に固執する、会社のやり方に従わない、結果としてミスが生じたりする、同僚が仕事をやりにくい、パワハラ・セクハラ、周囲に悪影響(関わりたくない等)といった問題がある場合が考えられます。
労働者の性格そのものを解雇事由とすることは通常許されません。しかし、具体的な問題のある勤務態度や言動等があり、指導したにもかかわらず改善せず、労働契約の継続を期待し難いほど重大な支障が生じる事態になったような場合には、解雇が有効になると考えられます。
少しコミュニケーションがしにくい、というレベル感では不当解雇になる可能性が高いので注意が必要です。
勤務態度不良や業務上のミスを理由とする解雇の例
欠勤・遅刻・早退を繰り返す、直前に連絡をしてくる、職務専念義務違反、就労時間中に私用メールやネットサーフィンをしている、指示を聞かずミスをするなどの例が考えられます。
注意・指導したにもかかわらず、改善が見られない等、勤務態度不良やミスが繰り返された場合に解雇が有効になると考えられます。
注意・指導をせずにいきなり解雇するのは不当解雇となる可能性が高いので注意してください。
非違行為を理由とする解雇の例
非違行為は様々ありますが、例えば、業務命令違反(転勤拒否、出向拒否など)、就業規則違反、競業行為・顧客奪取、金銭の私的流用(横領)、職場秩序・規律を乱す行為(暴力、脅迫)などの例が挙げられます
問題の非違行為が解雇に値するほど重大かどうか、また、その非違行為につき将来の是正・改善の見込みがあるか否かなどが考慮要素になり、解雇の有効性が判断されると考えられます。
この類型の場合には経営者の方も感情的になってつい「解雇だ」と言ってしまうことがあると思います。しかし、後で解雇が無効になると困るのは会社側です。一度、心を落ち着けて、弁護士に相談することが重要です。
解雇を行う際の対策:証拠はありますか?
上記のとおり、解雇には客観的合理的理由と社会的相当性が必要です。
そして、これらは、証拠によって示せるものでなければなりません。そのため、証拠の収集・作成が極めて重要です。
例えば、能力不足を理由とする場合に、どのように能力不足を立証していくかというところは大きな問題になります。能力不足というのは、主観的な要素が入り込むので、客観的に示すのは難しいからです。
このときに有効になるのが、PIP(Performance Improvement Program)です。これは、労働者のパフォーマンスが悪いことを理由に、一定の目標を設定し、一定期間に、目標達成や業務改善がなされたかを見極めるものです。目標設定とその未達を客観的に記録として残すことができるので、能力不足を理由とする解雇を行う場合に有益です。
また、解雇にあたっては、解雇通知書や解雇理由証明書も必要になり、会社としてどのような理由に基づいて解雇をするのかというところをしっかりと整理したうえで手続きを進めていかなければなりません。
この点をしっかりと確定しておかなければ、本来的には解雇をしていいかの判断もできないはずです。
法律で禁止される解雇
以上のような不当解雇の類型のほかにも、法律で禁止される解雇もあります。
例えば、次のとおりです。
・労働者が業務上負傷、疾病の療養のため休業している期間及びその後30日間は、解雇できません。
・産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって産前産後休業している期間及びその後30日間は、解雇できません。
・不当労働行為に該当する場合には解雇できません。(労働組合員であること、労働組合に加入し又は結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことを理由として解雇することはできません。)
・育児・介護休業法による措置の利用を理由に解雇することはできません。
労働者が正当な権利をすることを理由に解雇するのは絶対に避けなければなりません。
解雇が無効になった場合の金銭的リスク
解雇が無効になった場合、労働契約が継続していたということになり、その間の賃金を支払う義務を負うことになります(いわゆるバックペイ)。訴訟では判決までに長い時間がかかりますので、例えば解雇から1年半で判決が確定したとすれば、1年半分の賃金の支払い義務を負うリスクがあります。各社で賃金は異なるので一概には言えませんが、数百万円から1000万円近くなど、それなりの金額になってくることが想定されます。
実際には勤務していなかった人に賃金を支払うというのは避けなければなりませんので、解雇を有効に行えるかという検討をおろそかにしてはなりません。
不当解雇を避けるために:弁護士に依頼するメリット
解雇は労働者との対立が激しく、対応の慎重さが求められます。
解雇に関する知識が乏しいまま対応してしまうと、解雇が無効とされるリスクが増してしまい、会社として大きな金銭的負担を負うことにもなりかねません。
そのため、解雇を行う場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、事実確認のポイントを理解していますし、労働法・雇用契約や裁判例の調査・確認を行い、法的な分析を加えて、見通しや戦略についてのアドバイスをし、また、実際の対応・交渉を代理することもできます。
さらに、問題が解決したことを示す合意書・確認書を取り交わすことによって、後々の蒸し返しを防ぐことができますが、そのような合意書・確認書の作成も弁護士に依頼すればスムーズに進むと考えられます。
不幸にも裁判になってしまった場合でも、早期の段階から弁護士に対応の依頼をしておくことで、事実関係を整理した一貫した態度をとることができ、また、証拠のことを常に意識した対応をしてもらうことが期待できますので、裁判上不利な状況になるのを避けることができるはずです。
特に、対応・交渉中に主張がブレてしまい、裁判でその点を指摘されると、裁判官にもよくない印象を与えかねないため、一貫した態度をとることは非常に重要であると考えております。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、解雇への事後的な対応はもちろん、実際に解雇を行うにあたって不当解雇にならないように事前のアドバイスを行うことが可能です。
解雇にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。

 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |