

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「労働組合対策」についてのお話です。
「社内に労働組合があるが、これまでの対応は適切だったのだろうか?今後、同じように対応してよいのか?」
「従業員が外部の労働組合に加入したと聞いた。何か要求を受けたときにはどう対応したらよいのだろうか?」
このようなお悩みを抱えている会社は多いのではないでしょうか。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
当社はA社員を有期雇用契約(1年)により雇い入れています。何年か更新をしましたが、先日、更新はしない旨をA社員に告げました。
すると、A社員は、外部のB労働組合に加入し、B労働組合は当社に対して団体交渉を申し入れてきました。交渉事項は、A社員の契約更新についてのようです。
当社は、この団体交渉にどう対応するのが良いのでしょうか。
労働組合に加入したという情報を聞いたり、労働組合から団体交渉を求められたりしたような場合には、どのように対応すればよいのか分からず、不安に思うことも多いでしょう。
この記事では、団体交渉を中心に、労働組合への対応方法のポイントを解説していきます。
団体交渉とは
団体交渉とは、労働組合がその要求を、使用者と合意の上で実現するために、使用者と対等な立場で交渉するものです。
団体交渉の申入れを受けた使用者(会社)としては、自らが団体交渉を行う法的義務があるかを確認する必要がありますが、その際、①そもそも自らが団体交渉を受けなければならない相手方なのか(使用者性の問題)と、②労働組合の要求について団体交渉に応じなければならない事項なのか(義務的団交事項の問題)に分けて検討するのが有益です。
この判断を誤って団体交渉を拒絶すると、不当労働行為となってしまい、不利益な行為が法律上無効となる、労働委員会への申立を経て救済命令が発せられる、民事裁判が提起されるというリスクがあります。
したがって、団体交渉にどのように対応するかについては、慎重な判断が必要になります。
使用者性の問題
労働組合法(労組法)上の「使用者」は、団体交渉に応じる立場にあります(6条参照)。
そして、この「使用者」の概念には、組合員の労働契約の相手方の使用者だけではなく、実質的にそれに近似した地位にある企業も含まれると考えられています。
具体的には、構内業務請負に従事する請負企業の労働者について、発注企業が「使用者」に当たると考えられたり、子会社の労働者について、親会社が「使用者」に当たると考えられたりします。
ポイントは、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にあるかという点にあると考えられます。
実際の事例では個別具体的な判断をしなければなりませんが、「当社はその人と労働契約を結んでいないから、その人との関係では『使用者』にならない」と考えるのではなく、実質的に判断する必要があるということに注意しなければなりません。
上記の事例では、A社員は有期雇用契約ですが会社が雇用しているので、使用者性は認められると考えられます。
ポイント
上記とは別の議論で、労組法上の労働者の範囲についても議論がなされています。労組法は、労組法が適用される労働者を「賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者」(3条)と規定していますが、例えばフリーランスなどの業務委託・独立自営業者がこの「労働者」に該当するのかという問題です。この判断にあたっては、「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者の判断基準について)」(労使関係法研究会、平成23年7月)における考え方を踏まえて検討するのが有益です。裁判では、例えば、ウーバーイーツの配達員は個人事業主ではあっても労組法上の「労働者」と判断された一方で、フランチャイズのコンビニの店主らは労組法上の「労働者」には当たらないという判断がされています。このように、契約の形式・名称に関わらず、実質的に見て「労働者」と判断されれば、団体交渉を行う必要があるので、注意が必要です。
外部の労働組合
労働組合が特定の企業の従業員のみを組織していることが多いですが、複数の企業の従業員により組織されている労働組合もあり、例えば「〇〇ユニオン」、「〇〇一般労働組合」といった名前で活動しているものも見受けられます。
この場合、ある会社の従業員が所属していれば、その労働組合はその会社に所属する組合員の労働条件について、その会社に対し団体交渉権を有することになります。
上記の事例では、A社員は外部の労働組合に加入していますが、外部の労働組合であっても、A社員を雇用する会社は、団体交渉に応じる必要が出てきます。
義務的団交事項の問題
使用者は、労働組合からの団体交渉の申し入れに常に応じなければならない義務を負うわけではありません。使用者は、「義務的団交事項」について、団体交渉に応じる義務を負います(正当な理由なく拒否すれば、不当労働行為に該当します。)。
義務的団交事項は、一般に、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものと考えられており、非組合員である労働者の労働条件に関する問題についても、組合員の労働条件との関わりが強い事項は、義務的団交事項に含まれると考えられています。 少し複雑ではありますが、労働条件・待遇については団体交渉をしなければならないと考えていただくのが良いと思います。
上記の事例では、A社員の契約更新についての団体交渉ですので、組合員の労働条件その他の待遇に関するものとして、団体交渉義務を負う事項に該当すると考えられます。
団体交渉のポイント
以上のとおり、上記の例では会社は団体交渉に応じる義務を負うことになりそうです。
それでは、実際にはどのようなポイントに注意しながら団体交渉を進めていけばよいのでしょうか。
まず、会社は形式的に団体交渉に応じればよいのではなく、誠実に交渉する義務を負います(誠実団体交渉義務)。
そのため、労働組合からの要求については、できるだけ具体的な理由を挙げて回答するよう努める必要があります。また、団体交渉を行う日程について、合理的でない日程・場所を指定するのは問題でしょう。
他方で、使用者は、労働組合の要求を受け入れたり譲歩したりする義務はないと考えられますし、労働組合の要求に迎合してばかりいては要求がエスカレートしていく可能性もあります。また、従前と取り扱いを変えると、その点を不当労働行為と主張される可能性も否定できません。
したがって、会社は、使用者として、毅然とした対応を取りつつ、誠実な態度で(無下に拒絶するのではなく、適切に理由を説明する等して)交渉に応じるのが良いと考えられます。
団体交渉を放置することのリスク
使用者が義務的団交事項に関する団体交渉を放置したり拒んだりすることに、どのようなリスクがあるでしょうか。
上記のとおり、使用者は義務的団交事項について団体交渉に応じる義務があり、正当な理由なく拒否すれば、不当労働行為に該当します(労組法7条2号)。
また、誠実団体交渉義務を負ってもいますので、誠実な交渉を負わなければ、それも不当労働行為に該当することになります。
不当労働行為を行うと、相手方の労働組合は、労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行うことができます。団体交渉の状況を改善したとしても、救済命令の内容として、過去に団交拒否等の不当労働行為があった事実を確認し、今後同様の行為を行わないようにする旨の文書の交付や掲示等を求められる可能性もあります。このような救済命令が出されると、会社のレピュテーションに悪影響を与えることになりかねませんので、不当労働行為は行わないようにするということが非常に重要です。
さらに、労働組合は、団体交渉拒否・誠実交渉義務違反を労働争議(労働関係調整法6条)として、労働委員会にあっせん、調停、仲裁の申請を行うことができます。なお、あっせん、調停については、拘束力はありませんが、仲裁については拘束力があるとされています。
加えて、労働組合は、団体交渉拒否・誠実交渉義務違反について、裁判所に直接救済を求めることもできます。迅速な救済が必要になるため仮処分の申立てがなされることが多いと思いますが、仮処分についてはスピーディーな対応が必要になります。
また、使用者の団体交渉拒否・誠実交渉義務違反は、不法行為にも該当し得るので、労働組合及び組合員から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
このように、団体交渉を放置することは、会社のレピュテーションにも影響を与える重大な事態を招くことになりかねません。
労働組合対応を弁護士に依頼するメリット
上記のように、労働組合対応はセンシティブな問題であり、対応を誤ると不当労働行為として会社のレピュテーションが下がってしまうことにもなりかねません。
また、どのように対応したらよいかの勘所が分からない会社も多いと思います。
そのため、労働組合対応について、弁護士に相談することが考えられます。弁護士であれば、専門的な知識・経験を基礎に、以下のような対応が可能です。
- 団体交渉に応じる法的義務があるかの分析、アドバイス
- 団体交渉への同席
- 労働者や労働組合との交渉の代理
- 紛争対応の代理
それぞれについて少し説明を加えますと、弁護士は、事実確認のポイントを理解していますし、労働関連法や裁判例の調査・確認を行い、法的な分析を加えて、見通しや戦略についてのアドバイスをし、また、実際の対応・交渉を代理することもできます。
さらに、労働組合対応が終了した際には、個別の従業員との間で合意書・確認書を取り交わすことによって、後々の蒸し返しを防ぐことができますが、そのような合意書・確認書の作成も弁護士に依頼すればスムーズに進むと考えられます。
不幸にも裁判になってしまった場合でも、早期の段階から弁護士に対応の依頼をしておくことで、事実関係を整理した一貫した態度をとることができ、また、証拠のことを常に意識した対応をしてもらうことが期待できますので、裁判上不利な状況になるのを避けることができるはずです。
特に、対応・交渉中に主張がブレてしまい、裁判でその点を指摘されると、裁判官にもよくない印象を与えかねないため、一貫した態度をとることは非常に重要であると考えております。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、労働組合対応についての予防的なアドバイスはもちろん、事後的な紛争についてもアドバイスを行うことが可能です。
労働組合対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
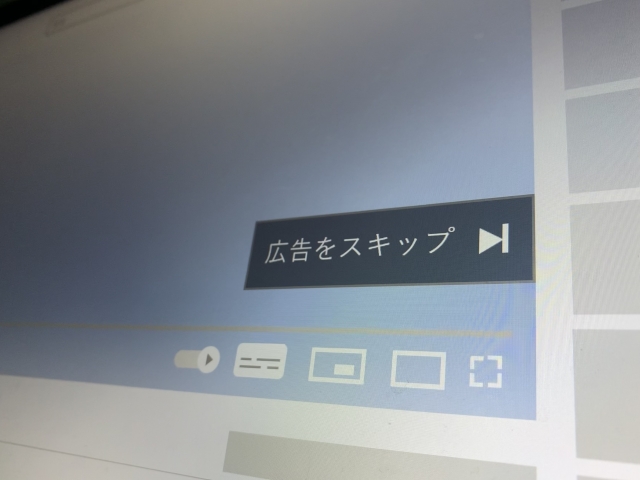
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

