
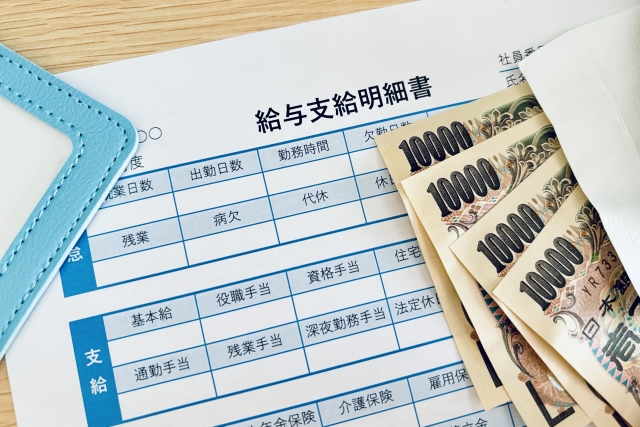
こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「残業代請求」についてのお話です。
「退職した従業員から残業代の請求を受けた。固定残業代で払っていたつもりだが、未払いはあるのか?」
「労基署から残業代の支払いがちゃんとできていないという指摘を受けた。どのように対応すればよいのか?」
このようなお悩みを抱えている会社は多いのではないでしょうか。
適切な労働時間の管理がなされていなければ、未払残業代が発生している可能性があります。また、一人からの請求であれば会社へのインパクトはそれほど大きくないかもしれませんが、複数人から一度に請求されると相応の支出が必要になり、会社経営の基盤に影響を与えかねません。
この記事では、残業代請求の考え方や対応方法のポイントをご説明します。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
当社では、従業員に毎月30時間分の固定残業代を支払っていますが、最近退職したA社員から残業代の支払請求を受けました。
固定残業代を支払っていたのに、A社員に対して別に残業代を支払わなければならないのでしょうか。
残業代の請求への対応方法を検討するにあたっては、労働時間・賃金体系の設計(就業規則や賃金規程の記載)、及び、実際の運用を踏まえて、請求の妥当性や反論ができないかを考えるのが有益です。
以下、詳しく見ていきましょう。
残業代とは?
なお、労基法上は、時間外労働(1日8時間、週40時間の労働時間規制を超える労働)、休日労働(週1日の法定休日における労働)、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)に対して割増賃金が支払われ、これを残業代ということもあると思います。
しかし、例えば、所定労働時間が1日7時間である場合に8時間働いたとしても、労基法上は割増賃金の支払いが義務付けられる時間外労働にはなりませんが、所定労働時間を超えた労働はしているので、当該時間に対する対価は支払われるべきです。
ここでは、そのような対価を含めるために、所定賃金に加えて支払いが必要となる労働に対する対価を残業代と考えることとします。
厚生労働省による公表によれば、令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
(1)件数:20,531件
(2)対象労働者数:179,643人
(3)金額:121億2,316万円
1事案における最大支払金額は2.7億円とされ、また、100万円以上の支払いについて指導した事業場数は1,335件に上り、相応のインパクトを受けた企業も多かったことがうかがわれます。
なお、残業代の消滅時効は、先般の民法改正により当面の間は3年間となりましたが、この3年間という取扱いは、本来は5年間とするはずのところを一時的に3年間としているものですので、将来的には5年間になっていくことが予定されているといえます。
そのため、今後、残業代請求によるインパクトは増大していくことが想定され、会社として看過することができない問題であるといえます。
労働時間・賃金体系の設計
残業代請求について考えるときに、まず重要なのが、会社としてどのような労働時間・賃金体系を採用しているかです。
上記のとおり、残業代を所定の賃金の他に支払われるべき賃金のことと考えると、労働時間をどのように設定しているかが重要なポイントになります。
一般的には、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で、「9時~18時(休憩時間は12時~13時)」のように決まった時間で定められることが多いと思いますが、例えば繁忙期があるような業種では変形労働時間制、柔軟な働き方を提案する場合にはフレックスタイム制の導入が検討されるでしょう。
また、例えば、1カ月の中で業務の繁閑が激しい業種であれば、1カ月の変形労働時間制を導入することで、閑散期には所定労働時間を短くし、繁忙期には所定労働時間を長くすることで、残業代の発生を抑えることができる可能性があります。
このように、労働時間の設計と残業代の請求とは、密接にリンクすることになります。
したがって、会社の業種や繁忙期の有無を踏まえて、一律の所定労働時間の設定ではなく、柔軟な労働時間制の導入をしたほうが、残業代発生のリスクを下げることができる場合があると考えられます。
また、そもそもの労働時間の把握が難しいという場合もあると思います。例えば、外回りが多く労働時間を算定し難いときには事業場外みなし制、業務の性質上その遂行方法を労働者の大幅な裁量にゆだねる必要があれば裁量労働のみなし制の導入が検討されるでしょう。
このような労働時間の算定についての特別ルールを利用することで、残業代発生のリスクを下げることができる場合もあると考えられます。
さらに、毎月決まった金額を残業代として一律に支給する固定残業代制度を導入している会社もあります。
しかし、固定残業代制度は、導入したからといって追加の残業代を一切支払わなくてよいということにはなりません。労基法どおりに算定した残業代が固定残業代を超過した場合は、超過した分を支払わなければならないとされているのです。
また、一般には、固定残業代制度が有効になるための要件として、①時間外手当や深夜労働の対価(割増賃金)の趣旨で支払われていること、②割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意されていること、③労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払うことが合意されていることが必要と考えられています。固定残業代制度が有効と認められないと、固定残業代が割増賃金の支払いではないとされて、別途割増賃金を支払わなければならないことになりかねません。
以上のように、固定残業代制度を導入するにあたっては、制度設計に不備がないかのチェックを入念に行う必要があります。
このように、(元)従業員から残業代請求を受けた場合には、就業規則や給与規程等を確認して、当該従業員がどのような労働時間制の下で勤務をしていたのか、また、どのような賃金体系となっていたのかを確認することが重要だといえます。
実際の運用
労働時間・賃金体系の設計を適切に確認できたら、次は実際の運用の確認が重要になります。
実際の運用としては、①適切な労働時間の把握と、②それに対する残業代の支払いが挙げられます。
まず、①適切な労働時間の把握について、労働時間をベースに残業代の計算が行われますので、その把握が重要であることはご理解いただけると思います。
そして、労働時間を把握するにあたっては、厚生労働省が出している「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえた対応を行う必要があります。その中では、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する原則的な方法として、(1) 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること、(2) タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが挙げられています。
なお、自己申告制も採用は可能であり、注意点も記載されていますが、結果として使用者に不利に働く可能性を否定できないので、おすすめはできません。
残業代請求を受けた場合には、労働時間を適切に把握することができていたかを確認する必要がありますが、残業代請求を受ける場合には、この労働時間の把握が十分ではないケースが多いと思います。そのため、できれば、残業代請求を受ける前に予防的に見直しをしておきたいポイントです。
次に、②労働時間に対する残業代の支払いについては、各人の労働時間制や所定労働時間、また、把握した労働時間に基づき、原則としては1分単位で残業代を支給する必要があります(例外的に、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められています。)。
したがって、残業代請求を受けた場合は、把握した労働時間に従って、不当な切り捨てをすることなく残業代を支払っていたことを確認することも必要になります。

個々人の請求への対応
以上の分析により、会社として支払うべき残業代の有無・金額の把握ができるものと思いますが、(元)従業員から請求される金額とは往々にして差異があると思います。これは、何を労働時間(時間外労働)と考えるかというところによるものが多いと思います。
そのため、個々人の請求に対応するにあたっては、(元)従業員の請求の内容をよく分析し、どこが会社の考え方と違うのかを明確にしていくことが必要になります。
また、もし(元)従業員が管理監督者であれば、そもそも時間外労働・休日労働への割増賃金の支払義務はないですし、一定の期間が経過しているため、消滅時効を迎えている残業代もあるかもしれません。
このように、残業代の請求の内容を分析し、会社として反論できるポイントがないかを確認しつつ、対応を行う必要があります。
残業代請求を放置するリスク:付加金・遅延利息
退職後の労働者から残業代の支払いを請求された場合には、原則として当該労働者が会社を退職した日の翌日から年14.6%の割合による遅延利息の支払いが必要になり、また、訴訟が提起され裁判所の判断を受けることになれば、付加金(最大で未払残業代と同一額)の支払いも命じられる可能性があります。
このような制裁的な制度も用意されておりますので、残業代請求に対しては、決して放置することなく、的確な見通しに基づいた対応を行うことが求められます。
弁護士による残業代請求対応、弁護士に依頼することのメリット
残業代請求への対応方法は上記のとおりですが、弁護士に依頼すれば、以下のようなアドバイスを受けることができます。
- 会社の制度を踏まえた、残業代請求の分析
- 残業代請求への反論の検討
- 証拠収集に関するアドバイス
- (元)従業員との交渉の代理
- 労働審判・訴訟等の紛争手続の代理
- 合意書等、解決の際に締結する書面の準備
- 今後のための改善策の提案(労働時間についての就業規則や賃金規程への記載方法のアドバイス)
残業代請求については、弁護士に相談し、対応を依頼することで、随時的確なアドバイスを受けることができます。付加金や遅延利息を踏まえると、争うことにより結果としてダメージが広がってしまうこともあり得るので、弁護士のアドバイスを参考にして、どのような対応を行うかを判断することは有益です。
また、不幸にも労働審判・訴訟になってしまった場合でも、早期の段階から弁護士に対応の依頼をしておくことで、労働時間制度や事実関係を整理した一貫した態度をとることができ、また、証拠を踏まえて相手方の立証の強弱を意識した対応をしてもらうことが期待できます。
さらに、残業代請求が制度の不備により発生したものであれば、当該制度は速やかに改善しなければ、さらなる残業代請求を生むことになりかねません。制度の変更に当たっては、就業規則の変更が有効に行われるよう、手続面にも配慮して行わなければなりませんが、弁護士であれば、制度の改善策・手続についてもアドバイスをすることが可能です。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、残業代請求への事後的な対応はもちろん、残業代発生のリスク回避のためのアドバイスを行うことが可能です。
問題社員対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
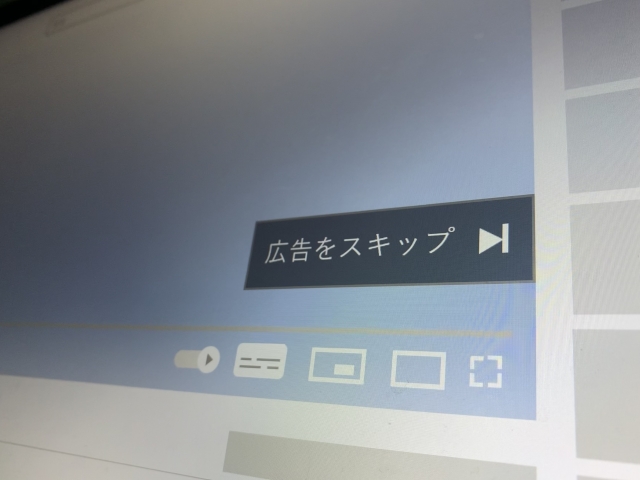
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

