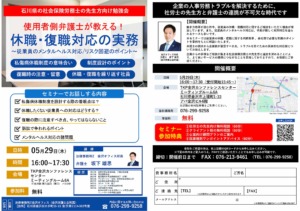こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。
今回のテーマは「就業規則」についてのお話です。
「うちの会社では就業規則を作成しなければならないのかな?」
「就業規則って何を定めればいいの?」
「就業規則は作成しておけばそれでいいの?」
このようなお悩みを抱えている会社は多いのではないでしょうか。
就業規則は、使用者により作成され、当該職場の労働者の規律と労働条件を記載したものです。
就業規則を作成することにより、賃金・労働時間などの労働の諸条件を、制度として画一的に設定することができるのです。
また、労働者が遵守すべき事項を記載しておくことにより労働者を規律することも可能になり、懲戒・解雇といった手続を行う場合には就業規則の定めが必要になると考えられます。
他方で、就業規則を作成しなければならないのに作成していない場合、罰金を科せられる可能性があり、また、例えば懲戒・解雇をしたいのにできないという事態に陥ることにもなりかねません。したがって、就業規則を作成していないまま放置するのは危険です。
この記事では、就業規則を作成する必要があるのはどのような場合か、また、就業規則で定めておくべき内容はどのようなものかについて、説明します。
例えば、以下のような事例を考えてみましょう。
従業員を雇い入れる際に、個別に雇用契約を締結していますが、就業規則は作成していません。
最近、問題社員が現れたため、当該社員を懲戒処分に付したいと考えているのですが、可能でしょうか。
目次
就業規則作成義務
まず、就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務を負います。ここでいう「10人以上」というのは、事業場単位で計算すると考えられていますので、例えば2つ以上の事業場があり、それぞれに6人ずつしか労働者がいなければ、就業規則の作成義務は負わないと考えられます。
また、「労働者」には、正社員、パート、有期雇用社員等、雇用形態にかかわらず当該事業場で働く労働者が含まれます。
したがって、上記の会社は、就業規則を作成する義務を負っているにもかかわらず、作成していないため、就業規則の作成義務違反の状態にあます。
就業規則作成義務に違反すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
就業規則の内容の分類
就業規則の内容は、大きく分けて3つに分類することができます。「絶対的必要記載事項」、「相対的必要記載事項」、「任意的記載事項」です。
絶対的必要記載事項とは?
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
これらを就業規則に定めておかなければ、就業規則の作成義務違反になります。
相対的必要記載事項とは?
相対的必要記載事項は、次の8つです。
①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
「~定めをする場合においては」という記載から、制度として行う場合に記載しておく必要があるという意味で、相対的必要記載事項と呼ばれています。
任意的記載事項とは?
絶対的必要記載事項・相対的必要記載事項以外の事項についても、就業規則に記載することは可能です。
そのような事項は、当事者が自由に定めることができ、任意的記載事項と呼ばれます。
例えば、就業規則の制定趣旨、解釈方針等が考えられます。
就業規則の具体的な内容
ここでは就業規則の内容のうち特に重要な絶対的必要記載事項について、その記載内容をもう少し掘り下げてみましょう。
絶対的必要記載事項は、あえて簡単に言えば、①労働時間・休日、②賃金、③退職・解雇についての定めということになります。
まず、①労働時間・休日についてです。
労働時間は、例えば、「始業時間:●時、終業時間:●時、休憩時間:●時~●時」というような形で定められます。
他にも、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制を導入する場合には、就業規則に定めることになります。
また、休日は、「土曜日、日曜日(法定休日)、祝日・・・」というような形で定められます。
労働時間・休日についての記載は、割増賃金(時間外労働、休日労働、深夜労働)を計算する上でも非常に重要なものですので、会社の実情を適切に反映しつつ、法令で求められる内容を漏れなく記載しておく必要があります。
次に、②賃金についてです。
賃金については、例えば基本給、手当、所定外賃金、賞与が考えられ、その詳細を記載していくことになります。
会社によっては、給与規程・賃金規程というように、就業規則とは別の規程で準備していることも多いと思います。これらの賃金についての規程は、就業規則の一部を構成すると考えられますので、適切に作成していなければ就業規則の作成義務違反になりますし、就業規則の一部として届出を行う必要もあると考えられるので、注意が必要です。
最後に、③退職・解雇についてです。
会社にとっても従業員にとっても、退職・解雇は非常に大きな問題です。
会社の立場から見れば、解雇したい従業員がいたとしても、就業規則に解雇についての記載がないと解雇ができないということになってしまい、大変困ってしまいます。
そのため、解雇に関する事項は必ず記載しておく必要があります。
具体的には、解雇事由、解雇の際の手続等を記載することになります。
なお、解雇に関連して、懲戒処分を行うときには懲戒事由を就業規則に定めておく必要があると考えられますので、派生的な問題ですが注意を怠らないようにしましょう。冒頭の例では、そもそも就業規則を定めていないということですので、懲戒処分ができない可能性があります。
就業規則作成義務がなければ、就業規則は作成しないほうが良い?
就業規則の作成義務がない事業場についても、就業規則を作成することは可能ですし、また、有益であると考えます。個々人ごとに雇用契約書を見なくとも、一律に適用される条件・規律が就業規則を見ればすぐわかるからです。
例えば、一人一人で解雇事由が異なったりすると、どの人がどの場合に解雇されるかで不平等感が生じてしまうかもしれません。また、そのような取扱いに合理性があるとも思えません。
就業規則には、会社としての管理・対応を画一化して無駄な労力・コストを減らすことができるという意味もあるのです。
また、個別の雇用契約により労働条件・規律を定めている場合、個々人との間で合意しなければその内容を変更することはできません。
しかし、就業規則を定めていれば、就業規則を合理的な範囲で変更することで、一律に労働条件・規律といった就業規則の内容を変更することができます。
どのような変更が合理的といえるかは、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情を踏まえて判断することとされていますので、会社が勝手な変更をできるというわけではない点には注意が必要ですが、画一的な運用を行う上では便利な手続になるでしょう。
このように、就業規則を作成しているからこそ受けられる恩恵もあるのです。
就業規則は作成さえすればよい?
就業規則は、作成さえすればよいというものではなく、いくつかの手続的ステップを踏む必要があります。
就業規則作成義務を負う会社について、就業規則の制定プロセスは、具体的には、次のとおりです。
①就業規則の文案の作成:就業規則の文案は、会社側で作成することになります。
②労働者代表の意見聴取:労働者の過半数を代表する者(過半数で組織する労働組合がある場合には当該労働組合)から、就業規則についての意見を聴取する必要があります。なお、労働者代表を選定する際には、形式的に会社が指名する人を労働者代表とするのではなく、実際に労働者の中から労働者代表を選出するプロセスを踏む必要があるので、注意が必要です。
③必要な機関決定:就業規則は会社の重要な規則ですので、その制定には取締役会決議などで承認を受ける必要があると考えられます。
④所轄の労働基準監督署長に届出:就業規則が作成できたら、労働者代表の意見書とともに、所管の労働基準監督署長に届出を行う必要があります。
⑤就業規則の周知:作成した就業規則は、見やすい場所に掲示、備付け、書面の交付、コンピュータを使用した方法により、労働者に周知しなければなりません。
就業規則の意見聴取義務、届出義務、周知義務に違反すると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
せっかく就業規則を作っても、これらの手続をしなければ不備があることになりますので、最後までしっかりと対応するようにしましょう。
就業規則の作成・チェックを弁護士に依頼するメリット
このように、就業規則については、(一定の場合に)作成義務があること、定めることにより効率的な労務管理ができるようになること、また、必要な懲戒権等の行使に当たっての根拠となることから、作成しておくべきものといえます。
また、適時に見直しを行い、最新の法令や現実の労務環境と整合しているかなどをチェックする必要もあります。なお、就業規則の変更を行うには一定の要件があるので、その要件をクリアしているかの判断も必要になります。
弁護士であれば、専門的な知識・経験を基礎に、以下のような対応が可能です。
- 会社として就業規則に記載すべき内容が記載されているかの確認
- 会社における運用実態を踏まえた就業規則の変更
- 就業規則の変更の可否の検討
弁護士は、実際に紛争になった場合にどのように取り扱われるかという観点からもアドバイスが可能であり、しっかり機能する就業規則を準備したいという場合には、弁護士に依頼して確認を求めるのが良いでしょう。
法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、就業規則の作成・チェックのアドバイスを行うことが可能です。
就業規則の作成・チェックにお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。
 | この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |
関連ページ


クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説
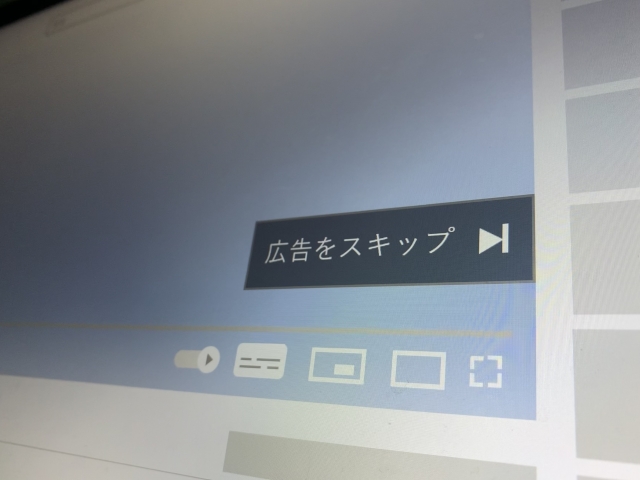
広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説